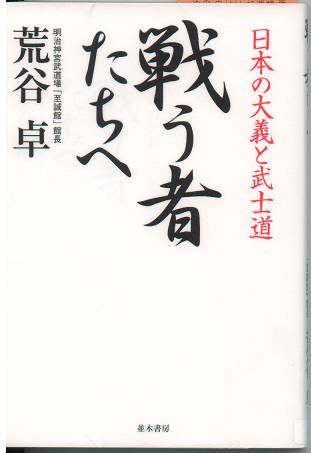
戦う者たちへ
日本の大義と武士道
武士道を身につけた兵士を養成できれぱ世界最強の特殊部隊ができる。
自衛隊初の特殊部隊創設を任された著者は、その行動理念を「武士道」に求め、技術だけでなく精神面においても精強な部隊を創りあげた。
初の実任務となったイラク派遣では現地で民心をつかむ日本的手法が高く評価された。日本の武道の目的は相手を殺傷することではなく、相手の邪気を清め、共存共栄の道を開くことにある。千年の時間をかけて創られた「武士道」の神髄に迫る。
三、戦わない日本人p27~31
米国に丸投げともいえる日本の安全保障は、『日米同盟基軸』という空虚塗言葉で語られるだけで、軍事機能として日本の安全を保障するような実効的メカニズムはまったく存在しない。米国による「核の傘」についてはよく話題になるが、実態は、核どころか通常戦力でさえ、日本の安全確保のために投入されるかどうか不透明なままである。「日本の安全を決めるのは日本自身で、日本の自由だ」という米国関係者の声をよく耳にするが、これに対する日本側の答えは、決まって「日本の安全は日米同盟基軸の堅持」だ。これは、自立した国家として、本当に自由な意思なのだろうか?
アメリカでは、ほとんどの組織に「スーパーバイザー(監督者)」がいて、常に社員や職員の状況を評価している。「自由にしていいですよ。でも、評価は下がりますよ」。一般には、これが恫喝の文句として使われている。逆に言えば、評価が下がろうが、対決しようが、自分の意思を通してこそ本当の自由が体現できるということでもある。
米国の特殊作戦の一つである心理戦関係者と話をしたおり、冒頭「日本が我々と同盟関係を維持するかどうかは日本人が決めることだ。君たちは自由だ。しかし、それによつて、我々が日本を叩きのめすという決断をするのは我々の自由だ」と切り出した。
心理戦の一端として言ったのかもしれないが、私には、戦闘者としての士気・戦意を高揚させる言葉であった。「私は、戦闘者として、自由なる日本のために戦うその日を待ち望んでいる」と答えた。戦う気概がなければ、真の自由は勝ち取れないのだ。
そもそも、日米同盟はいかなる機能を果たしているのだろうか?
少なくとも、日米関係は、冷戦終結を契機に明らかに変質している。
大東亜戦争終戦の時点において、アジアにおける米国のパートナーは蒋介石の中国であり、また、米国は早くから対日戦において毛沢東の中共とも協力関係にあった。
米国が、対日本開戦を意図して構築した『日本・日本人=悪』とする極悪非道なる存在としての日本観と日本人像は、戦前戦中を通じて、米国民だけでなく欧州各国の人々にも普及され定着しており、終戦時、そのような日本を米国の戦略的パートナーにするなどということは考えられなかった。したがって、日本の中核たる皇位継承権一皇族の範囲一を限定し、防衛力、経済力、産業基盤など国力のすべてを削ぎ落とし、自己保存能力もない集団として、一世紀後には跡形もなくなるような占領政策がとられた。
しかし、ソビエトとの対立が表面化するにいたって、米国の日本管理の方向性が百八十度変わった。その大転換を主張したのが、米国務省のジョージ・ケナンである。『フォーリン・アフェアーズ』(一九四七年七月号一に載ったケナンの「X論文」は、「(対ソ)封じ込め」論として注目を集め、たちまち米国の対ソ戦略へと昇華していった。
そのケナンは、「中国は、遠い将来にも強大な工業国・軍事大国になる見通しはない。一方、日本は、極東における唯一潜在的軍事・産業基盤を有し、勤勉な国民資質と反共思想、そして地理特性などから、対ソ戦略上のパートナーとして米国が防衛すべきLとして、マッカーサーの日本改革政策を経済復興政策に変更することを促した。冷戦構造の中で、日本は米国の期待にこたえた。日本領土内に米軍を展開させることによって、ソ連軍の戦力を欧州正面と極東正面の東西に分割させ、また、西側経済システムの重要な一員としての経済成長を遂げた。このように、米国の対ソ戦略上、日米同盟は軍事・経済面で特別に重要な役割を果たした。ところが、冷戦終結とともに、この戦略構造が消滅し、米国の戦略転換が訪れた。ケナンの予想に反して、中国は経済大国・軍事大国へと成長し、米国のパートナーとしての実力が備わつた。ソビエトと中国の決定的な違いは、ソビエトが米国と対抗的経済システムを構築したのに対し、中国は米国の経済システムの中に参入してきたことだ。一方、日本の経済力と在日米軍基地は、世界戦略上の意義を失うことになった。経済面では、いったんは強力な競争相手とみなされ、政治的関心が持たれたが、今や日本の経済再成長を期待する者はいなくなり、せいぜい、日本国民の保有する金融資産を国際市場に引き出して利用する程度の価値しか見当たらなくなった。在日米軍基地は、経費を日本が払ってくれるなど、特権ともいえる便利な仕組みがあるので、既得権として少しでも居座ったほうが有利だといったところか。こんな状況では、いくら日本側が経済・金融問題や基地問題で、米側に譲歩したとしても、日本の戦略的価値を高めるような効果はない。いくら『日米同盟基軸』を唱えて米国のご機嫌を伺っても、人問で言えば、いつまでも自立できない大人として、世界中の軽蔑を買うだけだ。
四、グローバリズムのもたらすものp32~35
ここまでわずか40ページ弱のページを紹介した、荒谷氏の想いが詰まった文章を私には、大胆に要約したり削ることが難しかった。このままでは、まるまる本書一冊をコピーしてしまいそうです。日本も含めてグローバル資本主義に巻き込まれた国際社会は、すべてが経済.金融を基軸に動いている。その経済.金融システムが、二〇〇八年秋に米証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻に端を発した金融危機によって瀕死の状態に陥った。これは、グローバル資本主義が進展すれば、当然予想できるシナリオであった。
米国では、「グローバル化により、失敗のリスクが大多数の者にもたらされ、富の恩恵は少数の者の手に集中され続ける。その結果、二〇一五年には二十八億の人々が貧窮以下の生活レベルにあるだろう」との専門家の意見もある。
これらの貧困層の人々の中には、「何もせずに死ぬのであるならば、戦ってから死にたい」と考える人もいるだろう。その一部は、この貧窮を生み出した「欧米社会を破壊してから死にたい」と考える。これが現在のテロリズムの特徴である。
米国の対テロ戦争は、米国流の極端な自曲競争を基本とする資本主義システムを地球上に浸透させることによって、必然的に増加するテロを抑制・排除し、さらにグローバル化を進展するという政治目的によって遂行されている。
つまり「テロとの戦い」とは、グローバル化戦略の安全を担保するための軍事戦略である。
世界で最も多くの資産を有する投資家の一人であるジョージ・ソロスは、『グローバル資本主義の危機』(1999年)の中で、次のようなことを述べている。
「資本主義と民主主義はその目的、計算単位、奉仕する対象が異なる。民主主義では、政治的権威を目的とし、市民の票が計算単位で、公共の利益を対象として奉仕する。これに対し、近代的な市場経済であるグローバリズムは、マネーの価値を最大にするための資本主義であり、その目的は富の獲得であり、計算単位はマネー、そして奉仕の対象は個人の利益である」さらに、「グローバル経済に巻き込まれた国家というものは、コスト削減のために社会保障制度、雇用制度など国民福祉を低下させ、資本の税金を減らさなくてはならない。政府が国家予算を維持するためには、消費の税金を増やす必要がある」と指摘している。日本においては、小泉政権下において、グローバル資本主義の真只中へ突入した。資本が国境を越えて自由に移動できるこのシステムでは、税金の高い国から安い国へと金融資産が動いていくので、日本も大企業や資産家に高い税金をかけられなくなった。その税収の目減りは、富裕層以外の人々から取るか、支出を減らすしかない。その結果、社会保障、雇用、福祉の低下はもとより、経済活動の主たるプレイヤーである企業の収益を増大させるため法人税を引き下げ、その補填は一般市民からガソリン税など大きな意味での消費税として徴収する。また、徴税機能としてサブプレイヤーに過ぎない地方公共団体の権限を縮小して、中央政府の権限や支配力を強化する方向へと進んだ。先進諸国の中で最も貧富の差が少ないといわれた我が国においても、米国のグローバル化に取り込まれたままでは、今後ますます富の格差が広がることは避けられない。ソロス氏はさらに「資本主義が、これまでマルクスが『共産党宣言』で指摘した悲惨な状態にならなかったのは、公共の利益を重視する民主主義によって阻止されたのだ」とも言つている。冷戦構造の考えのままの人は民主主義と資本主義はイデオロギーとして一体だと勘違いしているようだ。ソロス氏が指摘しているように、これまで国家においては、民主主義が資本主義の暴走を抑制していたが、グローバル市場には市場原理と呼ばれる資本主義は存在しても、民主主義は存在しない。個人の利益が唯一絶対的な価値を持ち、公共の利益という考えは存在しない。国家の政治が、グローバル市場の原理に焦点をあてて運営されれば、その国は、富を獲得したものだけが生き残る社会へと変質するのだ。
ここから先は、ご自身で本書をお読みください。

コメント