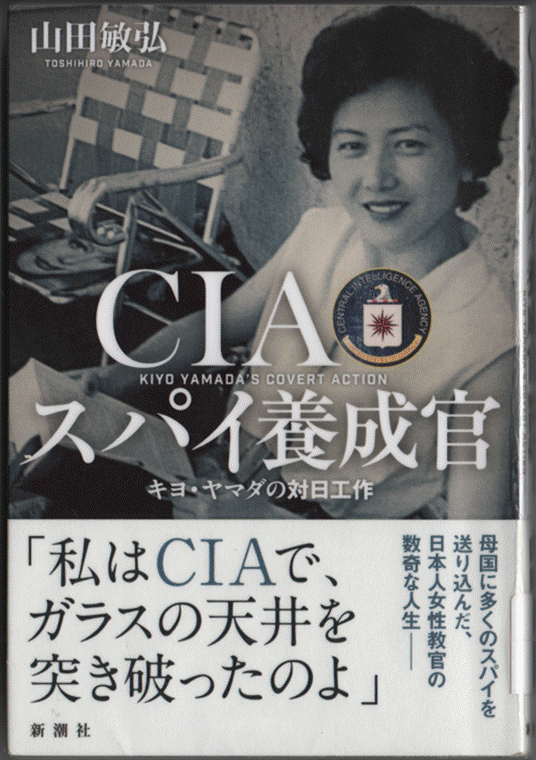
自分にとっては、大変面白い本で、久々に一気読みしてしまった。
しかしながら、帯にある宣伝文句「母国に多くのスパイを送り込んだ、日本人女性教官の数奇な人生―――」は、ちょっと違う。まったく数奇な人生ではない、裕福な家庭のお嬢様に生まれ、フルブライトで渡米し、幸せな人生を送ったストリーだ。「母国に優秀なスパイを悪意無く送り込んでしまった、東京女子師範出身のお嬢様が渡米し日米をまたにかけた幸せな人生」が正しい帯タイトルだと思う。
ちょうど、キヨヤマダは、私の知り合いのお嬢様出身の才女と重なってしまったせいで、たいへん面白い本であった。
優秀な女性だからと限ったわけではないが、人は天職に恵まれた時、幸せな人生を歩めるというものだ。彼女は才女で戦後間もない頃フルブライトプログラムで渡米し、結婚、CIAに入局したのは46歳であったにもかかわらず、彼女は自分の才能を伸ばし、77歳まで勤め上げた、具体的にはどの位の高位の地位なのかよくは分からないが、「私はCIAで、ガラスの天井を破ったのよ」と、自慢したのだから、CIAという組織の中で、女性だからと昇進を妨げる見えないが破れない障壁=ガラスの天井を破ったのだから、実務で相当高位の地位か権限を持ったことがあったのだろうと思う。単に退職時にメダルを貰っただけなら、奥ゆかしい日本女性であれば、ガラスの天井を破ったなどと言及しないであろう。
彼女の業績および影響力の結果として米国が、日米経済交渉などで、相当有利に働いたのであろうと推察される。バブル時代からの失われた20年、日本が凋落していった時代、日本を遣り込めた多くの優秀な米国CIA要員を沢山育てたことや、インテリジェンス活動も行い、たいへん優秀な実績をのこしたからであろう。日本が米国を越える勃興を防いだのは、優秀な日本人である彼女だったのである。
彼女はおそらく日本に対する悪意や恨みがあったわけでもない。ただただ、米空軍中佐だった夫に従って転勤するだけの平凡で退屈な主婦で終わるのではなく、自分の人生を切り開き、自分のためにキャリアを重ね邁進していった人生だったのであろうと思う。国家の思惑とか、思想に関係なく、ただ真面目に自分の仕事を突き進み、CIA内でキャリアを重ねた結果、インテリジェンスに耐性のない母国は、大きく凋落してしまっただけのこと、彼女が悪いのではなく、平和ボケした日本人全員が報いを受けたにすぎない。
おそらく、彼女は、彼女のせいで、日本が手玉にとられたことを悔いていないだろう。
裏表紙より・・・
キヨは世界を大きく変えるような目に見える変革や発明をもたらしたわけではない。前人未到の領域に到達し、派手に歴史を塗り替えた偉人もない。しかし、30年以上もの間、日本の歴史の舞台裏で暗躍してきたスパイを養成し、引退時事にはClAから栄誉あるメダルを授与され、表彰彰を受けるほどの評価と実績を残していた。
私が本書に対して当初期待したのは、GHQのジャック・Y・キャノン陸軍中佐やチャールズ・ウィロビーアメリカ陸軍少将と日本の吉田内閣との暗闘の裏話のような話だった。だが、キヨ・ヤマダ氏が活躍された時代はもう少し後の世代、70年代~80年代日米貿易摩擦の頃の話で、日本を遣り込めるのに活躍した要員を沢山育てたというだけの話なのだ。目次プロローグ 墓碑銘がない日本人CIA局員第一章 「私はCIAで、ガラスの天井を突き破ったのよ」突然の告白/「ラングレー」の局員/身近にいた日本人CIA局員/日本では理解され難い組織/日本語教官を超えた任務第二章 語学インストラクターと特殊工作日本国内におけるCIAの活動/教え子の述懐/対象が「困っていること」を探れ/沖縄返還問題での裏工作/ロッキード事件とCIAの闇/特殊工作への関わり第三章 生い立ちとコンプレックス東京の下町に生まれて/姉妹間のコンプレックス/家族へ抱いた嫌悪感/海外留学への夢/英語教師として教壇に第四章 日本脱出人生の転機となる出会い/米国への逃避行/異国での再会/移住を決断/アメリカに届いた母の訃報/日本人妻としての苦悩第五章 CIA入局センセイの思い出/言語を重視したCIA/アメリカ人に言語を徹底させる理由/CIA女性長官の経歴/採用試験の高い壁/日本語教官としての軋轢/競争させられる職場第六章 インストラクター・キヨ実践的な授業/教え子は、自分の子ども/日本での極秘教育拠点/優秀な教官として/同僚との軋轢/米ソ冷戦時代のCIA/バブル経済と日本/スパイのリクルーターとして/冷戦集結とリタイア第七章 最後の生徒日本で開かれた引退パーティ/晩年の生活/夫の発病/死後に分かった夫の秘密/悲しみの追い打ち/「病院では死にたくないわね」/モルモン教とCIA/最後のクリスマスエピローグ 奇妙な「偲ぶ会」主要参考資料
しかも、CIA内で、単なる通訳の仕事を超えたという詳しい工作の詳細は残念ながら述べられていない。夫の秘密とは、キヨとの間に子供を作ろうとしなかったのに、他の日本人女性との間に子供をもうけていた事を夫の死後知ったぐらいで・・・大きな波乱ではない。
おそらく、本書をまとめた山田敏弘氏も、もどかしかったかもしれない。
彼女のことを知る多くの人達が他界し、よく知る人達にも彼女は多くを語っていない。
P24-25
米国では、CIAで働いているという事実は、非常にセンシティブな情報だと見なされている。CIAに勤めていることが明らかになれば、致命的になりかねない。世界各地を回って情報収集や秘密工作などに従事する諜報員ともなれば、普段から他国機関に付け回され、監視されることもあれば、命を狙われることだってある。ゆえに局員が偽名や嘘の肩書きを使うのは普通になっている。正体がばれることは、すなわちスパイとしての死を意味するからだ。局員の身元は、どこから特定されるかわからない。本部勤務だった元CIA局員が自分の職場についてどこかで漏らしたりすれば、そこから海外の政府中枢などにいる協力者の身元特定につながることもありうる。というのも、その元局員の行動やコミュニケーションなどをつぶさに監視すれば、どこからか現役のCIA局員につながることもあるだろうし、さらにそこから別の局員たちの身元が特定されることけもなりかねない。これまでも、身元が敵対する国にばれたことで、命を落としたCIAスパイは数多い。最近では、二〇一〇年頃から、CIAが中国で使っていた現地のスパイが、次々と姿を消すという事件が起きている。彼らは、素性がばれたヱとで中国当局に拘束され、多くが処刑されていた。若干名は、CIAが資金を工面して中国国外へ脱出させることに成功したが、姿を消したスパイの数は三〇人を超えるという。この史上稀に見る失態により、中国におけるCIAの活動は、一時的に停止にされる事態にまで陥ったという。元CIAの諜報員が、中国国家安全部に情報を渡していたことだった。この人物はCIAを辞めた後、「IJT(日本たばこ産業株式会社)インターナショナル」の香港オフィスに勤務しながら、中国当局に情報を渡していた。また中国当局が、「COVCOM」と呼ばれるCIAの極秘通信システムに侵入していた可能性があり、そこからもスパイ情報が抜かれていたとの指摘もある。さらには二〇一五年に、中国政府系のハッカーが、米人専管理局(OPM)をサイバー攻撃して、連邦職員2210万人以上の個人情報や機密情報を盗み出している。そこにはCIAAが局員の入局に際して調べあげた個人情報なども大量に含まれていたとされ、そこから中国国内にいる協力者が特定された、との分析もある。このケースから、CIA関係者たちは常に危険と隣り合わせで任務に当たっていることがよくわかる。CIA本部には、ロビーにメモリアルウォール(追悼の壁)と呼ばれる壁があり、そこには身元が明かされるなどして殺害された職員たちの数を示す星が彫られている。現在、133の星があるその壁の前では、毎年、長官をはじめ現役局員たちが追悼式を実施するのが慣例となつている。
また、彼女が育てた子供達もしょの職務上、詳細を語ることはできない。
そんな中で、彼女の存在を発見し、まったくない資料を纏め上げた筆者山田氏の功績は大きい。
ちなみに、現トランプ政権の国務長官マイク・ポンペオ氏は2017年~18年に第24代中央情報局(CIA)長官を務め、CIA本部の、ロビーにメモリアルウォール(追悼の壁)の星の幾つかの追悼を行ったという。
ポンペオ国務長官が中国に対し厳しい理由がよくわかる。
あくまでも推測の域の話ではあるが、ロッキード事件に関して彼女の関わりに触れている。
p-53-55
特殊工作への関わりでは、ロッキード社による工作に、キヨが何らかの形で関与していたということはないのだろうか。そう水を向けると、ピートは、「彼女が日本で工作をしていたかどうかについて、真実が出てくることはないでしょう。ただこれだけは言えます。細かいところは話せませんが、日本にも渡航していたはずですし、何らかの協力をしていたと言ってもいいでしょう」キヨの知り合いや関係者などによれば、この頃、米国にいたキヨのもとへ、日本にいる諜報員からしょつちゅう電話や手紙などで連絡が来ていた。近所に暮らしていた友人のドイツ人、ヘルガ・トルダも、キヨが、「普段でも日本からよく仕事の連絡を受けていて、米国でやりとりをするために、夜中も仕事をしている」 と漏らしていたのを覚えていると言う。これには、背景がある。東京支局に属するCIA諜報員同士といえども、お互いに頻繁にやりとりをするようなことはない。ましてや、自分が何を追っているのかといった任務の情報も共有はしない。スパイの世界でよく言われていることだが、工作に関係している人たちがすべての情報を共有すると、一人が拘束されるなどすれば工作の全容がバレてしまいかねない。つまり、それぞれが自分の与えられた任務をこなしており、自分がどういう大枠の作戦に従事しているのかを知らないケースもあるのだ。そうした事情から、個人プレーでの判断を求められる局面が多く、米国にいるキヨを頼る者は少なくなかったという。関係者と接触する際に注意する点は何か、疑惑が取りざたされている政治家とのやりとりで注意すべき点は何か、アドバイスだけでなく具備的な指示を求めてキヨに直接、連絡を取っていた諜報員がいたということだ。日本との時差もあり、必然的に電話は夜遅くになったのだろう。実は、キヨはすでに述べたような新聞記者を取り込んだ作戦のみならず、後述するように、渡米前の戦前から戦後の日本で富裕層の家庭で育った頃の人脈もあったため、その流れから協力者の獲得という日本国内での特殊工作にも携わっていたという。「日本企業などに太いパイプを持っていた有力な日本人たちを介して、CIAに協力していた日本人スパイを、大手企業に送り込んでいた」との証言もある。キヨほもともと政府系だった企業などにも人脈を持っており、諜報員や協力者など情報提供や、就職斡旋にも関与していたのだ。生前のキヨを知る人たちによると、とにかくキヨはフットワークが軽く、「雑談で湧いて出たようなアイデアもすぐに実現に向けて行動に移すところがあった」と異口同音に言う。人を紹介した場合、その後ですぐに動いて、あっという間に大事な交渉をとりまとめた。ある元諜報員によれば、「もちろん、キヨが日本に来る際には、日本国内にいる知り合いの有力者などとも顔を合わせ、情報を仕入れて、諜報員らにも報告していた。企業文化などといったバックグラウンド情報も現場に伝えていた」 と言う。こうした話を総合すると、日本でCIAが関与していた様々な工作には、キヨがインストラクターという枠を超えて、その活動に関わっていたということが見えてくる。
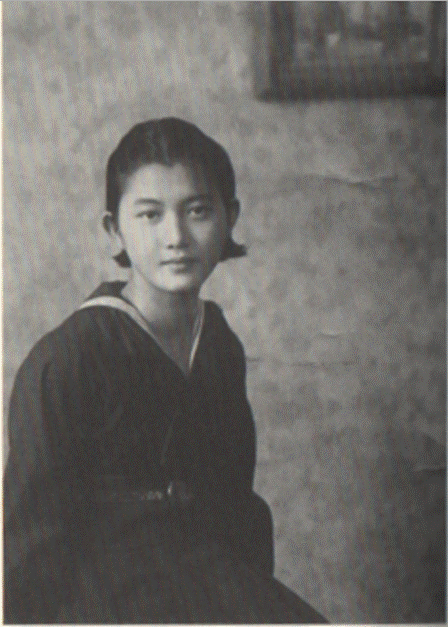
東京女子師範学校付属に通っていた頃のキヨ(昭和16~18年頃)なんて可憐な深窓のお嬢様!
下町で、代々続く老舗の肥料問屋のお嬢様として何不自由なく育つ。
優秀な姉と兄がいて、何かと比べられたりしていたが、それが家族を嫌い、渡米したい理由にしては説得力に欠ける。英語を専攻すれば米英文化に憧れるのはごく自然なことである。
戦後すぐには白百合で英語の教師として働き、宝塚の男役のような凛とした姿は、女子高生の憧れの的となった。
彼女が、日本国内に多くの人脈があった理由は、良い所のお嬢様は良い所に嫁ぎ、そういった関係から、日本国内にネットワークが形成されたのは自然なことである。
私の知り合いの女性は、JG出身だが、OG会の会にも頻繁に出席して人脈を持っている話を聞いたことがある。国会議員の奥さんだとか、医者とか官僚とかの奥様が多いとの事。
戦前の下町お嬢様が、当時憧れのフルブライトの留学生ともなれば、日本を離れてもいつまでも関係を維持できたことは納得できる。
【DIAMONDonline】窪田順生 2019.9.5 5:35
政界はもちろん、大企業やマスコミ、世論に影響を与える有名人に、それと知られずに近づき、意のままに操るCIA工作員。しかも、その工作員たちの「先生」は大正生まれの日本人女性だった。最近明らかになった、驚くべき真実とはーー。(ノンフィクションライター 窪田順生)■あなたの隣にもいる!?CIAの協力者の実態日本の大企業やマスコミ、政界などで今なお広く活動しているCIAのスパイたち。その先生は、なんと大正生まれの日本人女性だったある全国紙で活躍する記者が大怪我を負って入院した。と、ほどなくしてきちんとした身なりの外国人が病室にお見舞いにやってきて、こんなことを言う。「私はアメリカ大使館の政治担当オフィサーをしている者です。いつもあなたの記事を読ませていただき勉強させてもらっています。入院をしたと聞いて、いてもたってもいられなくなりお見舞いに伺いました」その後も足繁く通い、雑誌や食べ物などを差し入れてくるこの「親切な外国人」に、記者は徐々に心を開き、いつしか治療費などがかさんで今月ピンチだ、なんてグチまでこぼせるような間柄となっていた。そんなある日、米大使館員を名乗るこの男は、「お力になれるかもしれません」なんて感じで記者に「援助」を申し出てきた。気がつけば、この記者は取材活動の中で得られる日本政府や日本企業の情報を男に提供して、男が望むような記事を書く「協力者」となり、その関係はこの記者が「論説委員」になるまで続いたというーー。これは、ジャーナリストの山田敏弘氏が、日本で活動していた元CIA諜報員にインタビューして聞き出した「実際にあったエピソード」である。「CIA」といえば、多くの日本人は映画のように派手なアクションを繰り広げるスパイをイメージするが、実はその国の政治家、役人、大企業の社員、そして世論に影響を与えるマスコミや有名人などに接近して、知らぬ前に「協力者」(エージェント)へと仕立てあげ、情報収集や工作活動に利用する、というのが彼らの主な仕事である。つまり、あなたのデスクの隣にいる人や、テレビに出ているあの有名人も、本人にその自覚のないまま、CIAの「協力者」になっているという可能性もゼロではないのだ。と言うと、「そんな落合信彦のスパイ小説じゃあるまいし」「中国相手ならわかるが、同盟国で、子分のように尻尾をふる日本にわざわざそんな面倒な工作活動なんてしないだろ」とシラける方も多いかもしれないが、それは大きな間違いだ。我々が想像している以上に、アメリカは日本へスパイを送り込んでおり、ゴリゴリの工作活動に励んでいるのだ。その動かぬ証拠とも言うべき人物が、2010年に88歳で他界したキヨ・ヤマダこと、山田清さんである。■日本の大企業の中に大勢いる「CIAの協力者」大正11年、東京・深川の肥料問屋の家庭に生まれた山田さんは、東京女子大学の英語専攻学部を卒業して英語教師となった。終戦後に渡米してミシガン大学大学院で教育関係の修士号を取得。米空軍の爆弾処理の専門家と結婚してキヨ・ヤマダ・スティーブンソンとなり、20年ほど家庭で夫を支えていたが、46歳の時にCIAの「日本語講師」の募集に応募して見事合格した。そこから2000年、77歳で現役引退するまで、日本へ送り込まれるCIA諜報員に日本語や日本文化を教え続け、時には裏方として彼らの工作活動も支えたキヨ・ヤマダは、ラングレー(CIA本部)から表彰もされた「バリキャリ女子」の元祖のような御仁なのだ。ちなみに、冒頭のエピソードを明かした元CIA諜報員もキヨ・ヤマダの「教え子」の1人で、実はこの工作活動にも、彼女は裏方として関わっていたという。そんなスゴい日本人女性がいたなんてちっとも知らなかったと驚くだろう。それもそのはずで、アーリントン国立墓地にあるキヨ・ヤマダの墓標には「妻」としか刻まれておらず、CIAで働いていたこともごく一部の友人に明かしていただけで公にされていない。前出のジャーナリスト・山田氏がアメリカでCIA関係者や友人たちへ取材を繰り返すことで最近になってようやく、彼女が実は何者で、何をしていたのかがわかってきたのである。そのあたりは是非とも『CIAスパイ養成官 キヨ・ヤマダの対日工作』(新潮社)をお読みいただきたいが、その中でも特に興味深いのが、キヨ・ヤマダと、その教え子たちが行っていた工作活動だろう。同書には「キヨはもともと政府系だった企業などにも人脈を持っており、諜報員や協力者などの情報提供や、就職斡旋にも関与していた」と述べられており、以下のような証言もある。「日本企業などに太いパイプを持っていた有力な日本人たちを介して、CIAに協力していた日本人スパイを、大手企業に送り込んでいた」戦後の日本でCIAがこのような活動を延々と続けてきたということは、現在の日本の大企業の中には、キヨ・ヤマダの教え子たちに意のままに操られている「協力者」が山ほど潜んでいる可能性が高いということだ。彼らは自分がCIAの手先になっているという自覚すらなく、業務で知り得た情報を提供しているかもしれない。あるいは、CIA工作員が投げた「餌」に飛びついて、アメリカが望むようなビジネスをしているかもしれない。■対象が「困っている時」を狙え CIAの人心掌握術それがあながち荒唐無稽な話ではない、ということは、キヨ・ヤマダという女性の存在が雄弁に物語っている。一方で、いくらスパイとはいえ、そんなに簡単に人間を操ることなどできるわけがないのではないかと感じる方も多いだろう。実はCIAには、世界のビジネスマンたちも参考にする「人心掌握術」があるのだ。同書によれば、ポイントは「困っていることを探る」ことだという。といっても、弱みを見つけて脅迫をするのではなく、そこを突破口にして、あくまで自発的に協力をしてくれるように仕向けていくのだ。サイバー安全保障が専門である著者の山田氏は、冒頭のような新聞記者を籠絡した手口は「情報機関の常套手段」として、最近あったという事例を紹介している。「しばらく前に、コンピューターに不正アクセスをしてパスワードやクレジットカード番号を盗み出していたハッカーが当局に逮捕された。この人物を協力者にしようと考えた情報機関の関係者は、このハッカーの銀行口座などを調べ、かなりカネに困っていることを察知した。そして、保釈後、ハッカーに接触し、カネを提供するという約束をして、協力者にしてしまった」困った時に救ってくれた恩人からの頼まれ事は断りにくいというのは、人間ならば当然の感情だ。CIAをはじめとした諜報機関は、そこを巧みについて協力者に仕立て上げるという。あなたがピンチになった時、すっと手を差し伸べてきたその「優しい外国人」は、もしかしたらキヨ・ヤマダの教え子かもしれないのだ。
競争の激しいCIAの言語インストラクターではあったが、キヨのインストラクターとしての評判はすこぶる良かったようだ。
元教え子たちは「インストラクターとして優れている」「人柄も素晴らしい」ことから、
元教え子たちは「インストラクターとして優れている」「人柄も素晴らしい」ことから、
生徒たちにも人気があったと口を揃える。
p164-169
インテリジェンスに興味があり、インテリジェンス関係の本に、必ずと言って良いほど書いてある、日本にはインテリジェンスの概念がなく、だからダメだとインテリジェンスの本には必ず引き合いに出される逸話である。
ローレンスは述懐する。「バブル経済時には多くが日本語プログラムを志願した。重要な国を担当すると出世にもつながるからさ。もちろん、ウチの〃会社〃(CIA)も人員を増やして、日本でのスパイ活動は活発になったよ。どれほどの人員が東京にいたのかはわれわれも知らされなかったが、数百人はいたのではないだろうか。また世界的に有名な自動車メーカーがある地域にも人は送られていたはずだ」それは国務省でも同じだった。国務省で日本語を敢えていたファイファーも、こう語った。「国務省は入省するとまず希望を出します。当時咄、新しい職員の多くが日本に行きたいと希望を出したのです。日本語が大人気だった。職種的には、領事部とか、政治部、経済部とかの希望を出すのですが、政治や経済の部門は専門職になるので、言語の習得がキャリアにとっても非常に評価される。それで、じやあ君、書ず日本語勉強してこいと言われて学びにくる人も増えたのですが、難しくて音をあげる人も少なくなかった」ピートやローレンスのような、キヨが送り出して現場にいた教え子の諜報員たちは、日本に対する工作にも力を入れていた。その象徴的令は、1995年のアメリカと日本の自動車と自動車部品をめぐる交渉だ。当時は日米の貿易摩擦が深刻で、アメリカは日本の高級車に対する禁輸措置をチラつかせていた。米国のミッキー・カンター通商代表と橋本龍太郎・通商産業相による交渉は、当初、日米がお互いに自国での開催を主張した。結局、折り合いがつかず、スイスのジュネーブで行われることになった。六月二六日から開催された交渉では米国が有利に話を進めた。その理由は、CIA東京支局が徹底した諜報工作を繰り広げていたからだ。数週間前から、通信電波の盗聴などを専門とする国家安全保障局(NSA)のチームを現地入りさせ、盗聴の準備を進めた。そのおかげで、CIAは交渉に参加していた日本の通商産業省などの官僚や、彼らが電話で密に打ち合わせをしていたトヨタ自動車や日産自動車の交渉担当者との会話までを盗聴し、相手の手の内を掌握していた。毎朝、交渉の前に、カーターはその盗聴内容も含む最新情報についてブリーフィングを受けていた。日本側はそんなこととはつゆ知らず、悠長にも、ホテル備え付けの電話で連絡や打ち合わせをしていた。もちろん悪いのは盗聴するほうだが、あまりに警戒心がないのも問題だろう。ピートは「あくまで一般論ですが」として、「日本のように政官民が一緒になって動いていると、情報収集はやりやすいのだろうと私は思います」 と語っている。事実、ワシントンDCでは、日本大使館や日本企業のワシントン支社の電話ヤフアックス、日本政府や企業関係者の滞在するホテルですら、CIAなどによる盗聴の対象になっていたという。それまで冷戦構造の中でソ連とのスパイ合戦をしてきたCIAにしてみれば、「日本相手のスパイ行為は随分やりやすかったということですね」と、ピートは語った。特に経済分野は与し易いと感じていたようだ。八〇年代以降も、日本の首相が欧州なども外遊する際には、首脳の周辺にいるCIAの協力者から情報を得るために、CIA諜報員も現地に入った。キヨの教え子たちは、東京に拠点を置いて、こうした作戟に従事していた。そしてアメリカの経済政策を有利に進めるための工作に奔走しでいた。さらに元諜報貞らによれば、民間や政界、中央省庁などに協力者を作り、ハイテク電子分野や農産物分野の状況についての情報を吸い上げるなど、スパイ工作を存分に行っていたという。しかし、日本のバブル期にCIAの日本語プログラムでも起きていたこうした「日本バブル」は、とうの昔に終わっている。それに伴って、CIAでも日本語の人気は徐々になくなつていったキヨはのちに、親しい友人にこう嘆いていた。「二〇〇〇年あたりから、日本語プログラムの人気はかなり落ち始めたのよ。現在では、バブルの頃とは比較にならないほど、規模がずいぶん小さくなってしまったの。日本パッシングではないけど、重要度が低くなっていることは確かだつた。でも本当の問題はね、これが日本にとっても非常に残念な傾向だったということ。情報活動の世界の中でも、日本が軽視されることになってしまうから」キヨが言わんとしていることは、こうだ。CIAで「日本人気」が低下したことによる影響は、実は日本にもブーメランのように跳ね返って来るということなのだ。ローレンスも、こんなことを言っていた。「インテリジェンスの世界では、各国の間で 『ギブ・アンド・テイク』という考え方がある。つまり日本が、CIAをはじめとする外国の諜報機関や警察当局の欲しがるような情報をもっていれば、その情報と引き換えに、日本が欲しい情報やテクニックなどを他国から手に入れやすくなるのだ」この話は、日本側の当局者からも聞いたことがある。その当局者によれば、「各国の情報当局同士で、こちらから情報をあげるから、例えばそちらの国のメーカーの、この情報を教えてほしい、というやりとりがあります。もしくはメーカーとは関係のないような情報が欲しい時もあります。以前、日本で、事件の証拠品である日本製のハードディスクを海から回収したが、塩水でディスクが劣化し、中の重要な証拠を見ることができないというケースがあった。そこで日本の当局は、製造元である日本メーカーに協力を要請し、そのディスクから情報を抜き出す技術を世界に先駆けて開発したのです。日本メーカーだからこそ、当局に全面協力をしてくれた。そのおかげで他の国ではできないテクニックを、日本は手にしました。そのメーカーのハードディスクは世界的に人気も競争力も高く、かなり普及していたため、外国の当局者にその技術の話をすると、ぜひそのやり方を教えて欲しいという要請が来るようになった。そしてその情報を与える代わりに、こちらの欲しかった情報を提供してもらうよう交渉できたのです。例えば、ノキアの携帯から情報を抜き出すテクニックを知りたければ、フィンランドにこちらの技術を提供してから協力してもらう、といちた具合です。日本のメーカーが強ければ、情報を欲しい国の当局者が寄ってくることになる」 逆を言えば、日本のメーカーに世界的な競争力がなくなれば、世界から日本は情報を求められなくなる可能性がある。そうなれば、情報は「ギブ」してもらえなくなる。つまり、日本の技術力や経済力が衰退するこどのインパクトは、インテリジェンス分野にも波及する。CIAで日本の人気がなくなるというのは、日本が「使えない国」「重要度の 償い国」だと思われていると捉えることもできる。キヨは、そうした背景を踏まえた上で、日本語プログラムの衰退を嘆いたのだった。
日米交渉における日本のインテリジェンス警戒心の欠如からくる日本側の大失態である。
常に情報は筒抜けで、交渉は米国に常に有利にコントロールされ、国益を失い続けてきた。
その日米交渉で、常に米国に出し抜かれていた理由がやっとわかった!山田清氏の存在だったのか!
【デイリー新潮】2019年10月24日掲載
2015年8月、米バージニア州アーリントンは抜けるような青空が広がっていた。筆者は首都ワシントンD.C.で開催されていたシンクタンクの会議を終え、あとは当時暮らしていたマサチューセッツ州ボストンへ戻るだけだった。だが、帰途に就くまえに、以前からどうしても気になっていたアーリントン国立墓地に立ち寄ることにした。アーリントン国立墓地を訪問してみたいと思ったのは、知人女性との雑談がきっかけだった。以前、D.C.近郊で暮らしていたというこの知人は、その当時に「興味深い女性」と知り合ったと話した。在米の日本人主婦が、友人だけを集めて開いた、小規模なホームパーティでのことだったという。知人が直接聞いた話によれば、その女性の名は、キヨ・ヤマダという。日本で生まれ育ったキヨは、戦後しばらくして渡米し、アメリカ人と結婚。そのあと、アメリカの諜報機関であるCIA(中央情報局)に入局した――。初めて知人からこの話を聞いた2014年の時点で、キヨ・ヤマダはすでに他界し、アーリントン国立墓地に埋葬されている、とのことだった。そこで、D.C.への出張に合わせて、初めてアーリントンを訪れたのだった。***これは最近上梓した拙著『CIAスパイ養成官―キヨ・ヤマダの対日工作―』(新潮社)(https://amzn.to/2P8dhJI)からの抜粋(一部修正)だ。このノンフィクション作品では、戦前に生まれた日本人女性が、軍国主義的な時代の日本の中で育ち、日本という国を一変させた戦後の混乱期に日本を離れ、米国で諜報機関に入っていく軌跡を追った。日本語インストラクターとして入局したCIAでは、対日スパイ工作にも関与するなどして、局内で多大な評価を受けていた。キヨの教え子たちは、沖縄返還、ロッキード事件、反共産主義工作、日米貿易摩擦などで指摘されているCIAによる戦後史の裏で暗躍し、さらにキヨ自身も日本での工作活動を支えたり、スパイをリクルートするなど諜報工作にも関与していく。日本の有力者を諜報員に紹介するようなこともあったという。出版後、拙著に対する様々な反応に触れている。そんな中でも興味深かったのは、CIAで対日工作に関与したキヨ・ヤマダが「売国奴」だったのではないかというものだった。ある著名人からも、インターネット上でこの本こそ「売国の実態」であるとコメントをいただいた。拙著の取材では、米国人だけでなく、米国へ移住した外国人たち、そして米国に移住した日本人など多くに話を聞いた。そんな彼らとの対話を通じて、日本のみならず、欧州から移住して米国に暮らす人たちの苦悩なども耳にした。移民大国の米国ではあるが、移民の多くは、簡単には越えられない「米国人」の壁を感じ、心の奥深くでどこか疎外感を抱いているのが印象的だった。そんな社会の中で、キヨ・ヤマダはCIAで自分の居場所を見つけることになるのだが、そのあたりの詳細は拙著に譲りたい。結局、彼女はCIAで対日工作を行った「売国奴」だったのか。取材から見えたキヨ・ヤマダは確かに米諜報機関の手先として働いていたが、彼女の人生を紐解いていくと、「売国」という言葉では片付けられるものではないことがわかる。俯瞰すれば、対日工作を行っていた時点で、日本人から見れば「国を売った」という印象を受けるだろう。ただ日本とアメリカの関係においては、そんな単純な構図では括れない。そもそも戦後の日本が世界から奇跡的と言われる経済発展を遂げ、現在は経済的に失速して「失われた時代」が続いている状態ではあるが、世界的に見て裕福な国家になれたのも、米国が日本にもたらした対日工作があったから、という側面もある。もちろん、日本の政治家などの中には、戦後に日本人である矜恃を失わないよう米国と対峙しながらこの国を形作ってきた者もいたが、それでも、米国が日本に軍事・安全保障の面で「傘」と「安心」を与え、日本人がそれを甘んじて受け入れ、恩恵に与かってきた事実は消せない。そのおかげで、日本は経済分野にリソースを集中させることができたのである。米国からしてみれば、それは反共政策という自分たちの利害のためだった、としてもである。そして、そんな日本のあり様を受け入れ、民主主義国家の日本で、米国に依存する日本を作り上げたのは私たち日本人に他ならない。つまり米国なしには独り立ちができない日本は、日本人自身の選択の結果なのである。そう言う意味では、日本という国の安全をアメリカという他国に委ねた私たちは皆、「売国奴」だと言えるのではないだろうか。一方で、筆者が取材で会った米国に移住した日本人の中には、戦前に生まれ、戦後間もなく米国に渡った人たちも多かった。彼らは米国で厚い壁を感じながら、日本人である自分のアイデンティティを強く持ち続けていた。■生き様例えばキヨ・ヤマダと親しかった年配の日本人女性2人にインタビューをした際に、こんなことがあった。取材後、自動車で訪れていた筆者に、この女性たちは行きたいところがあると言う。そこで一緒に、D.C.の郊外にあるバージニア州フェアファックス郡の郡政府センターに向かった。実は同センターの敷地内にある公園の片隅には、第2次大戦で日本軍に強制されたとされる従軍慰安婦のための記念碑が設置されていた。探すのに苦労するほど離れた一角にあったこの記念碑は、D.C.の韓国系組織であるワシントン慰安婦問題連合が、この地域に暮らす韓国系住民だけでなく、議会議員などにもロビー活動を行って2014年に設立を実現させたものである。フェアファックスの記念碑を前にして、彼女たちは首を傾げながら、こういう石碑は「信じられないことよね」「許してはいけないと思うわ」「なぜこのような物を作るのか、目的がわからない」と嘆いた。帰りの車の中でも、彼女たちは「もちろん韓国系の友人もいる」が、「日本は詫びて、戦後に時間をかけてすべて解決してきたことではないのか」と熱く語っていた。彼女たちとのやり取りでは、日本人としてのアイデンティティを強烈に持っていることを痛感させられた。彼女たちは、身の回りには日本製品を置き、日本車に乗り、出来る限り日本食を食べている。仕事をきっかけにして米国には移住したが、やはり日本への想いは強い。米国という「人種の坩堝」の中にいるからこそ、周りから「日本人」の代表として扱われ、日本人であることを強く意識することになる。その中で日本の良い面も悪い面も、それぞれが考えるようになるのである。筆者が会ってきた人たちを見ると、そうした経験を通して日本人であることを誇りに思っている人が多かった。海外に長期間暮らした日本人の多くが「日本びいき」になるという話を聞いたことがある人も多いだろうが、そういう背景があるのだろう。そして、それはキヨ・ヤマダも一緒だった。彼女は晩年、CIAに入って「初めて米国に受け入れられたと感じた」という言葉を残している。そんな彼女も、自動車は常に日本車だった。遺品からは、長く疎遠だった家族の写真などだけでなく、数多くの日本語の新聞の切り抜き、山田家の過去帳や数珠、日本で卒業した大学の証書など日本らしいものが次々と出てきた。明治から大正時代の詩人、上田敏による『上田敏詩抄』なども大事に保管されていた。日本の文化や歴史に関する本もたくさん遺されていたという。彼女の人生には、「売国奴」などという言葉では言い表せない生き様があったのである。もっとも、彼女は自分の可能性を信じて米国に留学し、思いがけず主婦になって、後にCIAに入ったが、自分の人生を懸命に生き、置かれた環境でベストを尽くしただけに過ぎない。こうした背景を踏まえて、キヨ・ヤマダという日本人女性が本当に「売国奴」だったのか、もっと言えば「日本とは一体どういう国なのか」というところまで、拙著から考えるきっかけにしてもらえれば、と願わずにいられない。山田敏弘国際ジャーナリスト、米マサチューセッツ工科大学(MIT)元フェロー。講談社、ロイター通信社、ニューズウィーク日本版などに勤務後、MITを経てフリー。著書に『ゼロデイ 米中露サイバー戦争が世界を破壊する』(文藝春秋)、『モンスター 暗躍する次のアルカイダ』(中央公論新社)、『ハリウッド検視ファイル トーマス野口の遺言』(新潮社)、訳書に『黒いワールドカップ』(講談社)など。数多くの雑誌・ウェブメディアなどで執筆し、テレビ・ラジオでも活躍中。週刊新潮WEB取材班編集

コメント