中共ウイルス の患禍は世界経済を飲み込み、現在世界的食糧危機が懸念されております。
世界は少なくとも過去50年間で最悪の食糧危機の瀬戸際に立っていると2020年6月に国連は発表された食糧安全保障と栄養へのCovid-19の影響に関する国連報告書において警告し、大惨事を回避するために迅速に行動することを世界各国政府に求めました。
報告書において食料の収穫は豊作であり、穀物などの主食の供給は「強固」とありますが、しかし、世界的流通網の混乱に対して脆弱です。パンデミックとロックダウン封鎖が食糧を収穫、売買する人々の流れと食料の流通を妨げているため、かつてないほど脅威にさらされていると国連の報告書は述べています。
また、2020年8月中国の習近平は「飲食店での浪費をやめ、節約習慣をしっかり育てよ」という、いわゆる「食べ残し禁止令」を突然出した。
報告書において食料の収穫は豊作であり、穀物などの主食の供給は「強固」とありますが、しかし、世界的流通網の混乱に対して脆弱です。パンデミックとロックダウン封鎖が食糧を収穫、売買する人々の流れと食料の流通を妨げているため、かつてないほど脅威にさらされていると国連の報告書は述べています。
また、2020年8月中国の習近平は「飲食店での浪費をやめ、節約習慣をしっかり育てよ」という、いわゆる「食べ残し禁止令」を突然出した。
武漢ウィルス研究所で発生した中共ウイルスと三峡ダムが決壊寸前となった長江域の大洪水のほか、米国との貿易戦争で経済が大失速、戦狼外交の弊害によりオーストラリアとの食肉輸入制限もあって、現在中国国内は深刻な食糧危機となっているようだ。
現時点の食糧問題の主なものは、食料の偏在と、グローバル化した流通網が、バンデミックの影響から食糧生産の担い手である季節労働者の流れと食料流通網が寸断さたり、バッタの大量発生による蝗害、異常気象等による一部困窮国家に食料がいきわたらないという一時的現象がおきている。
しかしながら、世界が21世紀に食糧危機に陥るとする説は、「世界人口の急増」「農地の拡大の限界」「水資源の制約」「化学肥料を用いた農業の持続可能性への疑問」「緑の革命の終焉」「開発途上国における飼料需要の急増」などを理由に、繰り返し懸念されれている。
環境破壊は進み、結果気候変動をもたらし、自然災害が多発しており2050年には100億を超える地球の人口を支えられるのか誰もが漠然とした不安を抱えていることも事実です。
1798年、英国の経済学者マルサスは、人口論を著した。その中で、「人口の増加が生活資源を生産する土地の能力よりも不等に大きいと主張し、人口は制限されなければ幾何級数的に増加するが生活資源は算術級数的にしか増加しないので、生活資源は必ず不足する」、という帰結を導き、欧州各国による植民地獲得競争に拍車をかけた。
世界各国の元国家元首の政治家、外交官、産業人、自然・社会科学者、各種分野の学識経験者などが集まり、1968年4月に立ち上げのたスイスに本部がある民間団体ローマクラブが、資源と地球の有限性に着目し、マサチューセッツ工科大学のデニス・メドウズを主査とする国際チームに委託して、とりまとめた研究で1972年に発表された「成長の限界」において、「人口増加や環境汚染などの現在の傾向が続けば、100年以内に地球上の成長は限界に達する」と警鐘を鳴らしている。
しかしながら人類は、たゆまぬ努力を重ねてきた。マルサスが人口論を論じた時点では肥料は伝統的な有機質肥料が中心であり、単位面積あたりの農作物の量に限界から農作物の量が人口増加に追いつかず、人類は常に貧困に悩まされるという現象は自明であったが、1900年以降にハーバー・ボッシュ法などで化学肥料が安定供給されたことにより一時的に克服された。
成長の限界が発表された、1972年の世界人口は約39億人、2019年が77億人と世界人口は約2倍になったが、その間に食肉生産量は約4倍に増やした。つまり、約50年前にくらべて、世界の人々は平均で約2倍の肉を食べている。やがて到来するであろう100億の人口を支えるカギは、現在フードテック呼ばれる新たな技術にかかっている。
そのいくつ
また、最近魚介類の高騰が気になる、日本近海での乱獲は海産物の資源が枯渇しつつある。
私は、西暦2000年私は佐賀市に住んでいた。当時近所のスパーで冷凍の中国産ウナギのかば焼きが特売時1串100円、通常150円で売っていた。
2005年私は京都に住んでいた、京都市内は物価が高かったが、スーパーでは冷凍スルメイカは1杯100円であった。
2015年サンマは1匹50~80円が相場であった・・・
現在ウナギのかば焼きは中国産でも1串400~500円、冷凍スルメイカはピンキリだが1杯300円、サンマは格安でも120~150円。
イワシ、サバも高級魚の仲間入りだ、かつてのニシンやホッケ、ハタハタも塩鮭も大衆魚であった。
世界は日本食の美味しさに気が付いてしまい、海産物需要が急増している。海洋資源の枯渇が年々深刻な状態になっている。2050年一般大衆が海産物を食べることはできなくなる恐れがある。一皿100円の回転ずしはどうなってしまうのか?
昨年フードテックがマーケットで話題となり、日経産業新聞ではフードテック特集記事が組まれた。なかなか秀逸な記事です。参考までにコピペしておきます。
【NIKKEI BUSINESS DAILY 日経産業新聞】2020年12月27日 5:33
植物肉では米ビヨンド・ミートが先行する先端技術で食分野に革新を起こす「フードテック」が芽吹き始めています。世界の人口増に伴う食糧難や畜産で生じる温暖化ガス、消費者の環境・健康志向……。新型コロナウイルスの感染拡大で、食料生産国が輸出を制限する動きに警戒も強まりました。人の命に欠かせず、豊かな生活の実現に必要な食料をどのように持続させるか。日経産業新聞は「実れ フードテック」の連載企画をこの春に立ち上げました。テクノロジーの進化で食の課題に挑む企業の現場に迫ります。これまでの連載をまとめました。発芽した大豆の抽出物を分析装置にセットする先端技術で食分野に革新を起こす「フードテック」が芽吹き始めた。世界の人口増に伴う食糧難や畜産で生じる温暖化ガス、消費者の環境・健康志向……。新型コロナウイルスの感染拡大で、食料生産国が輸出を制限する動きに警戒も強まる。人の命に欠かせず、豊かな生活の実現に必要な食料。「実れ フードテック」ではテクノロジーの進化で食の課題に挑む企業の現場に迫る。初回は植物肉の知られざる開発の最前線を追った。「新型コロナが長期化した際、食料の安定供給の観点からもフードテックの議論を進めていく必要がある」。17日、農林水産省がウェブ会議システムを通じて開いた「第1回フードテック研究会」。日本ハムや不二製油グループ本社など約80の企業・団体150人以上が参加し、ぱく質供給に関する課題について議論を繰り広げた。研究会の参加企業のなかに「植物肉の魔術師」と関係者をうならせる注目のフードテック企業がある。その名はDAIZ(ダイズ)。2015年に熊本市で創業されたスタートアップだ。植物肉の新規参入企業の多くが出来合いの植物肉のもとや大豆を外部から調達するのに対し、DAIZは植物肉原料となる大豆を発芽させるところから挑む。栽培技術を究め、多彩な味を編み出す様は魔術師さながらだ。魔法の種は市内の起業支援施設に構える研究所にある。足を踏み入れると、冷蔵庫のような外観の栽培装置が7基並ぶ。研究員が1基の扉を開けると中には20本の試験管がずらり。それぞれに小ぶりなクリーム色の大豆が数粒ずつ入っている。栽培装置ごとに酸素や二酸化炭素(CO2)の濃度と温度を変えて、異なる産地、品種の大豆を芽が出るまで育てる。この発芽が風味を左右する。約16時間かけて発芽する間に大豆のうまみ成分のグルタミン酸の量は通常の5~10倍に増えておいしくなる。■緻密なデータ分析 約700種類の成分を研究「隠し味」は緻密なデータ分析にある。研究所で芽が出た大豆は液体成分を抽出し、分析装置にかける。研究員が画面のグラフを見つめ、味や香りなどを左右する約700種類の成分を分析する。うま味や甘みに関係するグルタミン酸などのアミノ酸量が発芽条件でどう変わるかを見極める。発芽した大豆の抽出物を分析装置にセットする落合孝次執行役員は「人工知能(AI)を使い、地道な分析で少しでも本物の肉の味覚や食感に近づく道を探している」と話す。大手食品会社を経て、米国でバイオベンチャーを立ち上げた経験がある落合氏は、DAIZの研究開発の要だ。研究所で最適な栽培法などがわかった大豆は、熊本県益城町の工場で植物肉のもとに加工する。鶏肉風、牛肉風、豚肉風――。本物の肉の味に近い植物肉のもとを、ここまで細かく作り分けられるのが強みだ。アミノ酸含有量が異なる複数の大豆を最適な比率で混ぜる「秘伝のレシピ」がそれを可能にしている。「エクストルーダー」と呼ぶ装置で熱や圧力、強いひねりの力を加え、水蒸気爆発させてポップコーンのように膨らませれば完成だ。記者も試食した。小籠包(ショウロンポウ)は割ると肉汁があふれて本物と遜色のない味わい。唐揚げもジューシーで完成度は高いと感じた。DAIZは果実堂を設立した井出剛社長と落合氏の出会いから生まれた。「穀物として眠っている状態の大豆ではなく、目がさめて遺伝子が動き始めたばかりの発芽中の大豆に目を向けてください」。落合氏の言葉で井出氏は植物肉のアイデアをひらめき、17年に開発を始めた。現状、市販をしていないが、20年6月に既存工場で量産を始め、外食店や食品メーカー向けに供給する。21年には約10億円を投じ、新工場も設ける。DAIZに出資するニチレイフーズとは冷凍食品を開発する計画。23年に植物肉だけで売上高30億円をめざす。井出氏は「狙うは日本最大の植物肉会社」と語る。■フードテック 国内外で勃興、世界の食糧需給の行方に危機感
フードテックが国内外で勃興している。植物肉に代表される代替肉のほか、人工的に魚を育てる養殖、品質を保持してうまみも引き出す熟成、食品の味をおとさずに長期保存する冷凍技術、ゲノム編集技術を用いた食品など裾野は広い。背景にあるのは世界の食料需給の行方への危機感だ。農水省によると、50年に穀物や畜産物など世界の食料需要は58億トンと10年に比べ1.7倍に膨らむ見通し。所得階層別にみると、低所得国の需要が2.7倍に急増するとみられる。世界人口は50年に15年より3割多い97億人となり、人類は「たんぱく質不足」になる恐れがある。足元では新型コロナの影響でロシアやウクライナなど食料生産国が供給を制限する動きも出始めた。自国優先主義が広がれば、将来を待たずに食料危機が現実味を帯びる。どう危機を乗り切るか。有力な解決手段として植物肉が浮上する。畜産物需要は推定6~7割増えるが、牛肉1キログラムを得るのに約10キログラムの穀物飼料が必要となるなど環境負荷は大きい。牛のげっぷや家畜の排せつ物から出るメタンガスは二酸化炭素(CO2)の25倍も温暖化への影響があるとされる。気候変動の一因と目されるなか、環境負荷の低い植物肉は、菜食主義者も多い欧米で「脱ミート」の波に乗った。調査会社ジオンマーケットリサーチによると、新規参入が相次ぐ植物肉市場は、18年に119億ドルだったが、25年は212億ドルになりそうだ。植物肉では米ビヨンド・ミートが先行する植物肉で先行する米ビヨンド・ミートは19年5月に植物肉専業として初めて米ナスダック市場に上場。スイスのネスレは19年に欧州で大豆と小麦が原料の植物肉のハンバーガーの販売を始めた。日本では植物肉をうたう商品が店頭に増え始めたのはここ1年のことだが、食品素材メーカーの老舗企業も動き出した。19年秋、大丸心斎橋店(大阪市)の植物肉総菜店「アップグレードプラントベースドキッチン」に大豆由来の総菜がずらりと並んだ。ひき肉や豆乳ベースのチーズが原料のラザニア、唐揚げなどに来店者は舌鼓を打った。植物肉への関心を高める消費者との接点を増やす狙い。仕掛け人は不二製油グループ本社。1960年代から植物肉の研究を始め、外食向けなどに豆腐ハンバーグといった植物肉を供給してきた。植物肉のもとである大豆たんぱく素材の国内市場で約5割とシェアは首位だ。素材供給という黒子に徹していたが、消費者向けにも進出をうかがう。不二製油の直営店は19年、大丸心斎橋店に開業。現在は緊急事態宣言に伴い休業する(大阪市)本業のBtoB(企業間取引)でも植物肉を取り扱いたい企業からの相談が引きも切らず、7月に千葉市に新工場を稼働させる。強みは一日の長がある技術力で、植物肉のもとは粒状型で50~60種類をそろえる。温度や圧力の設定だけでなく、食感を出すのに使うでんぷんなど副原料の配合方法にノウハウがある。フル稼働が続く大阪府の工場と2カ所で増産する。プラント・ベースド・フード・ソリューションズ事業部門の芦田茂シニアマネージャーは「肉に近づけるだけでなく、大豆由来ならではのあっさりした味の良さを生かしたい」と、強みの大豆の味に徹底してこだわる。日本でも消費者の健康志向を背景に高たんぱく・低カロリーな食材として大豆の注目度は高まる。新旧の食品メーカーが入り乱れ、技術や味を競い合う。世界の胃袋を満たす日本発の植物肉カンパニーが生まれるか。食の未来を巡る競争の幕が上がった。(企業報道部 古沢健、大阪経済部 川原聡史)
・植物肉、迎え撃つ日ハム・伊藤ハム 日本の味で勝負3月末、東京駅改札内の商業施設「グランスタ」の弁当エリアに大豆ミート専門の店舗が現れた。伊藤ハムグループの伊藤ハムフードソリューション(東京・目黒)が期間限定で開いた店舗だ。「大豆ミートのそぼろ弁当」や「大豆ミートのハンバーガー キーマカレー」などの植物肉を用いた約20の商品が並んだ。伊藤ハムが「グランスタ」に開いた店舗では「大豆ミート」の弁当などを販売した「想像以上に肉っぽい」「肉を使っていないことに気づかない」。商品を購入した消費者から寄せられた感想に伊藤ハムは植物肉を用いた食品メニューの完成度に自信を深めた。4月18日からはJR錦糸町の駅ビル内の直営店でパン類や弁当の販売を始めた。順次、販売網を広げる方針だ。食肉国内最大手の日本ハムも3月、大豆を用いた家庭向け植物肉の新ブランド「NatuMeat(ナチュミート)」を立ち上げた。植物肉を使った総菜のほか、ハムやソーセージを展開する。ソーセージでは大豆に加え、こんにゃくを用いるのが特徴。より食感をジューシーにするなど工夫をこらして勝負する。植物肉市場は欧米で盛り上がりをみせるが、日本でも普及の兆しが見え始めた。国内では食肉とは畑違いの大手食品メーカーで植物肉市場参入の動きが広がるなか、長年食肉加工のノウハウを培ってきた日本ハムや伊藤ハムなど食肉大手も相次ぎ新規参入に動く。食肉を巡る危機感が老舗を新分野への挑戦に突き動かす。日本ハム・ソーセージ工業協同組合(東京・渋谷)によると、国内の食肉加工品の生産数量はここ数年横ばいが続き、2019年は18年比0.6%減った。最近は物流コストが増え、消費者の低価格志向で小売店での価格競争も激しい。さらに伊藤ハムの春名公喜・事業戦略統括部長は「世界で食肉需要が増え、供給不足や価格高騰が懸念される」と語る。■植物肉 日本の新規参入組 大豆の扱いで一日の長
食肉大手にとって、植物肉は自社のビジネスの脅威にもなりかねない。だが、日ハムの畑佳秀社長は「世界的に人口の伸び以上に食肉需要が高まっており、植物肉がすべて食肉と置き換わることはない」と指摘。むしろ、日ハムは危機から転じ、日本が植物肉の世界で飛躍するチャンスがあるとみる。カギを握るのは日本伝統の食文化だ。日本フードアナリスト協会の横井裕之理事長は、「日本は精進料理などの文化があり、大豆を扱うのは得意だ。植物肉は世界的に有望な市場となるので、さらなる発展を期待できる」と話す。畑氏も「日本では豆腐をはじめ、大豆たんぱくが重宝されてきた。植物肉は新たなたんぱく質のメニューになる」と意気込む。実はニッポンハムグループは魚や高たんぱく質の乳製品を展開し、たんぱく質を供給している。食肉をはじめ、多様なたんぱく質食品を提供する総合食品メーカーとして成長する戦略を描く。植物肉を有力な武器に育てたい考え。日本ハムは15年から外食向けに植物肉を提供し、研究開発を重ねてきた布石は打っている。日ハムは大豆ミート以外でも、細胞培養技術を持つインテグリカルチャー(東京・新宿)と19年に連携し、培養肉の基盤技術開発を進める。安定した製造技術の開発につなげるため、日ハムの肉製品の製造ノウハウを、インテグリ社に提供する。ただ、欧米が植物肉の実用化では先行している。米ビヨンド・ミートや米インポッシブル・フーズは大手ファストフードチェーンと組み、植物肉を使ったハンバーガーなどを販売して人気を集める。ビヨンド・ミートの19年の売上高は18年比3.4倍となった。スイスのネスレや米ケロッグのほか、米食糧大手のカーギルなど資本力のある食品メジャーも続々と新市場開拓に乗り出した。ビーガン(完全菜食主義者)やベジタリアン(菜食主義者)、健康のために肉を食べる回数を減らす「フレキシタリアン」といった欧米で流行する食文化も植物肉の普及を後押しする。■植物肉元年 日本勢 ニッポン流の味付けで対抗後発の日本はどのように対抗すべきか。横井氏は「大豆ミートは味と食感の両方でまだ改善の余地がある」とし、「大豆だけでおいしくするのは限界がある。たとえば、こんにゃくや寒天の粒子に肉のエキスを染み込ませて混ぜ味を強くするなど、新しい発想が必要だ」と提言する。日本は世界の多様な食文化を「消化」し、独自に発展させてきた歴史がある。カレーやラーメンなどはその代表例だろう。植物肉でも日本流の「味付け」が始まった。植物肉を手掛ける国内メーカー「ゼロミート」ブランドでハンバーグを18年秋に投入した大塚食品は味の改善で試行錯誤を続ける。「食感、味、香りのどれか一つだけ満たしても本物の肉には全く近づかない」。新規事業企画部の嶋裕之部長は強調する。顕微鏡や味覚測定器で肉のハンバーグの食感や味を科学的に分析。粒の形や大きさを近づけ、パルミチン酸など脂肪酸の割合も似せると味や食感が近づいていった。植物肉の課題は大豆臭さを消すことだ。濃い味付けなどで覆い隠す方法もあるが、塩分が強くなる。そこで大豆原料を処理する工程や原料の配合、ソースの味を工夫することで大豆臭を低減させ、香りを肉に近づけた。伊藤ハムは3月に立ち上げた「まるでお肉!」シリーズで食肉加工のノウハウを注ぎ込んだ。「大豆ミートのメンチカツ」など揚げた商品を加えたのが特徴だが、味付けの仕方や油脂の使い方、食感の出し方にも苦労したという。日ハムの植物肉のハンバーグは香りにこだわる。デミグラスソースのような濃厚さとは違う、カレーに近いスパイシーな味わいを意識し、爽やかな香りのするオレガノなどの香辛料を使った。食肉メーカーとして培ってきた香辛料で肉の臭みを消すノウハウが植物肉の開発にも生かされた。培養肉や、卵を使わないマヨネーズやクッキー生地、液卵を開発する米ジャストに出資するなどフードテックを有望な投資先と位置付ける三井物産。吉川美樹専務執行役員は「日本的なセンスで疑似肉を提供できる。商品開発にいま取り組んでいる」と明かす。食品や外食業界で、20年は日本で植物肉普及の元年になると言われる。テクノロジーはあくまで手段。料理の世界ではどんなに素材が良くても調理の腕前次第で味は変わる。フードテックも問われるのは、技術を使いこなす経営の腕前とセンスだ。FRDジャパンの十河COOはサーモンの陸上養殖で食糧危機の解決を目指す(千葉県木更津市)世界的な人口増と乱獲で水産資源の枯渇が懸念されるなか、食分野の課題を先端技術で解決するフードテックで養殖にイノベーションを起こす動きが広がる。天然魚の漁獲量の頭打ちに直面するが、海のない陸上で魚を養殖したり、環境に配慮した餌で養殖による海洋汚染を軽減したりする。「実れ フードテック」の第2部では、新しい養殖技術で豊穣(ほうじょう)の海の恵みを目指す旗手たちの現場を追う。千葉県木更津市。鳥がさえずる上総丘陵にFRDジャパン(さいたま市)の養殖場がある。東京湾から10キロメートルほど離れた内陸部で、バイオテクノロジーなど先端技術の研究所が立ち並ぶかずさアカデミアパークの一角にたたずむ。2018年に稼働し、同社が「プラント(工場)」と呼ぶトラウトサーモンの陸上養殖の実験場で、1日当たりの換水率を1%未満に抑える「完全閉鎖循環式」を編み出した。■魚の陸上養殖、食料危機問題解決の切り札に
FRDジャパンは「海に依存しない陸上養殖の商業化」を掲げる養殖スタートアップの旗手だ。天然海水や地下水を使わずに、水道水をほぼ100%循環させて養殖する新方式に挑んでいる。プラント内に入ると、配管や網目状の歩道が張り巡らされた大部屋の足元に16の飼育槽が並ぶ。のぞき込むとそれぞれ数百尾が円を描くようにグルグルと同方向へ泳いでいた。大きさや餌の食べっぷりなど、サーモンの「性格」で分けている。自動給餌機の先のパイプが突如くるくる回り始めた。粒状の餌が空気圧で吐き出され、丸々育ったサーモンが食いつく。FRDジャパンの飼育槽には数十尾のトラウトサーモンが養殖されている(千葉県木更津市)さいたま市のふ化場から持ち込むサーモンは初めは体長20センチメートルで200グラムにすぎないが、9カ月かけて大きいものでは60センチメートル、5キログラムまで育つ。切り身にして地元のスーパーや飲食店に出荷する。試食すると食感やうまみは天然物と遜色ない。「陸上養殖は問題解決の切り札になる」。十河哲朗最高執行責任者(COO)は強調する。三井物産の新規事業の立案制度を経て独立した。十河氏の視線の先にあるのは、将来の食料危機問題だ。地球で人口が増え続けており、たんぱく源の不足が将来、懸念されている。十河氏は「魚、牛、豚、鳥とたんぱく源の候補は数あるが、人口100億人時代は魚が有力」と指摘し、「陸で魚を養殖できるようになれば、社会にインパクトを与えられる」と目を輝かす。実際、魚の需要は旺盛だ。国連食糧農業機関(FAO)によると、16年の世界の養殖業の生産量は1億1000万トンにのぼり、天然の水産資源の漁獲量の9200万トンを上回る。発展途上国では人口増と経済成長で魚の消費量が増え続ける。半面、水産資源は乱獲による枯渇の危機に直面する。FAOによると世界の水産資源のうち3割以上が乱獲状態だ。漁獲枠に余裕のある水産資源量は漁獲量のわずか6%。養殖なしでは世界の食卓をまかなえない「たんぱく質危機」が迫る。頼みの綱の養殖だが、従来の洋上養殖は自然環境に左右される。地球規模でも適した漁場は国内では三陸海岸、海外ならノルウェーのフィヨルドなど入り江の多い穏やかな海に限られる。例えば、サーモンはノルウェーとチリが養殖の世界生産の8割を占める。餌などによる海洋汚染や生態系破壊も深刻だ。養殖場所や生産量の制限もあり、増産余地は限られる。代替技術として陸上養殖もあったが、採算性の壁に普及は阻まれてきた。水の取り換えや水温調節の電気代などでかさむコストが課題だった。FRDジャパンは水を取り換えない陸上養殖で、この壁を崩しつつある。■バクテリアで水質を維持、水道水をほぼ100%循環して養殖
カギは水質を維持するバクテリアだ。独自のろ過層で魚の排せつ物に含まれる毒性の高いアンモニアを硝化細菌で毒性の弱い硝酸に変える。この硝酸も一定量たまると、魚の病気の原因になる。独自開発の脱窒処理装置で、脱窒菌を用いて硝酸を窒素に変える仕組みも加えた。従来方式は硝酸を減らすため、1日約3割の水を替えていた。人体では血液が常に体を循環し、腎臓などで血液をろ過する。FRDジャパンは水質やバクテリア量、給餌タイミングなどをIT(情報技術)で制御。「低コストで最適な生産のため、条件を変えながらデータを積み重ねている」(十河氏)新方式は水道水に塩分やミネラル分を加えて海水を再現し、蒸発分のわずかな水の補充で済む。水を取り換えると、海水から病原菌を水槽に持ち込むリスクが上がるうえ、育成に適切な水温に調節する電気代が増える。新方式は電気代も大幅に下げられる。十河氏は「上水道があれば陸上養殖できる」と強調する。現在の実験プラントは年30トンで約1万匹を養殖できるが、この規模では採算が合わない。21年度以降、40億~50億円を投じ商用プラントを建てる。さいたまのふ化場も統合し実用段階に入る。年1500トン、約50万匹相当を出荷する計画だ。課題は大規模化した際のコスト低減だ。コンパクトで効率的な設計が肝となる。水槽なら八角形と円形では水中の酸素のムラやよどみの起きやすさが異なり、机上だけでなく実地で確かめる。ろ過槽も設備の配置方法や規模を見極めている。エンジニアリング技術が重要なため、大手エンジニアリング会社から技術者を招いた。洋上養殖のサーモンは設備投資が少ない一方、日本やアジアなど消費地までの物流コストが重い。「日本で陸上養殖しても近距離のアジアでは価格競争力はある」と語る。将来、陸上養殖のサーモンが量産されれば、日本の消費者は手ごろな価格で舌鼓を打てそうだ。「魚が死んでおしまいだよ」。13年の創業当時に陸上養殖は無謀とみられ異端扱いされた。ようやく、陸上養殖サーモンが食卓に並ぶ光景が現実味を帯びてきたが、日本のサーモンの年間輸入量は約20万トン。まだ、彼我の差は大きい。十河氏は「本当の挑戦はどれだけ低コストでおいしい魚を育てられるかだ」と力を込める。■□■□■陸上養殖、水産大手や海外企業も触手 SDGsが後押し丸紅と日本水産はデンマークの陸上養殖に強いダニッシュ・サーモンを共同で買収魚の養殖は海洋汚染や生態系破壊につながる恐れがある。国連が定めた「持続可能な開発目標(SDGs)」や、環境や社会などに配慮した企業を選別する「ESG投資」の流れが強まるなか、水産会社や海外企業も陸上養殖の事業化に動く。鳥取県米子市。遠くに大山を臨む日本海沿岸の陸地で、国内初のマサバの大規模陸上養殖の試験に取り組むのが日本水産と日立造船だ。6月8日、大型トラックの荷台から伸びたホースから飼育槽に、次々とマサバの稚魚が注ぎ込まれた。FRDジャパンの「完全閉鎖循環式」と異なり、飼育に使う水は施設の地下からくみ上げる海水を入れ替えながら循環させる。地下水のため水温は一定で、冷やす電気代を抑えられる。飼育槽とろ過槽を結ぶ配管は外気や日光で水温が上がらないよう地下でつなげた。地下海水ならマサバの沿岸養殖でネックになるアニサキスに犯される心配もない。「1カ月も持たないのではと心配したが、1カ月半たった今も順調に育ちほっとしている」。日本水産の平山健史・養殖事業推進課長は語る。年240トンを見込む出荷の第1弾は来春。無事に育て上げるには、大きくなるにつれペースが速まる水質悪化の制御が欠かせない。これを支えるのが日立造船の浄化技術だ。同社はし尿の浄化や水族館の水質管理で実績がある。汚水のアンモニアをバクテリアで浄化する際に、強みの高効率ろ過技術を生かす。バクテリアは担体と呼ぶ素材に付着するため、その表面積が大きいほど浄化効率が高まる。表面に凹凸を加えた独自の担体で「効率が上がる」(平山氏)。陸上養殖に関わる企業の裾野は広がる。マルハニチロは山形県でサクラマスの陸上養殖実験を進める。商社では三井物産がFRDジャパンに約85%を出資するほか、丸紅と日本水産は4月、閉鎖循環式の陸上養殖に強いデンマークのダニッシュ・サーモンを共同で買収した。■海外勢、陸上養殖で大規模プロジェクトを計画海外勢ではオスロ証券取引所に上場するアトランティックサファイアやノルディックアクアファームズなどが陸上養殖に取り組む。アトランティック社は米フロリダ州で年9万トンのサーモンを陸上養殖する巨大プロジェクを進める。米国はサーモンの一大消費地でもある。ノルウェーや米国勢は桁違いの規模感で進む一方、日本ではまだ小規模なのが現状だ。FRDジャパンの十河哲朗最高執行責任者(COO)は「どこが最初に収益化にこぎつけるかの競争に突入している」と指摘する。シンガポールの投資ファンド傘下のソウルオブジャパン(東京・港)も三重県で年1万トンのサーモンの陸上養殖を計画し、23年にも出荷する予定だ。投資マネーも流入するなか、戦いは熱を帯びてきた。(企業報道部 逸見純也)・衛星データで餌やり新潮流、ウミトロンが狙う養殖革新餌を制する者が養殖を制する――。餌は魚の成長を左右するうえ、魚の種類によっては養殖コストの6~7割を占めることもあるからだ。餌やりは重労働で、水の汚染源にもなる。餌は課題の宝庫で、ここでイノベーションを起こせば、ビジネスとしてうまみがある。餌と向きあい、餌やりの効率化や環境配慮タイプの開発に企業が挑む。陸上養殖が広がるが、養殖の現場は依然、海が中心だ。海は水温や塩分の変化、赤潮の発生など自然現象にさらされる。海の状況を宇宙からつかみ、養殖業者に届け始めたのがシンガポールに本社を置く養殖スタートアップのウミトロンだ。■データを駆使し、餌やりを効率化
7月に立ち上げた新サービス「ウミトロンパルス」は、人工衛星の情報を使い、専用サイトで海水温や塩分濃度など魚の生育管理に必要な海洋データを確認できる。養殖場に近い局所的なデータも見られる。養殖業者がデータを駆使して海の状況を適切に把握できれば、効果的な餌やりにつながる。例えば、赤潮発生時に餌をやると魚が酸欠で死にやすくなる。赤潮接近が事前にわかれば餌を止められる。無駄な餌が減れば赤潮の拡大も抑止し、海洋汚染の防止にも役立つ。世界の養殖業者や漁協、研究者の利用を想定し、すでに国内外から数十件の登録がある。当日データだけなら無料。月額30ドル(日本円で約3200円)の有料プランは過去のデータまで閲覧でき、48時間以内の変化を予測する機能を備える。ウミトロンが宇宙に目をつけたのは必然だった。共同創業者の藤原謙代表は宇宙航空研究開発機構(JAXA)で人工衛星を開発していた。三井物産に転じ新規事業を開発していたときには農業の衛星データ活用にも触れた。藤原氏は成長する養殖分野に目を付け、2016年に創業した。22年には藤原氏の母校の東京工業大学などと組み、海洋観測システムを搭載した小型衛星を打ち上げる計画もある。プランクトンなどの情報を高解像度で観測し、魚類や貝類、藻類の養殖に生かす。ウミトロンパルスとの連動も見据える。宇宙に突き進むウミトロンだが、活動の原点は地に足をつけた「餌やり革命」にある。全国で白い箱形の装置が置かれた養殖いけすが増えている。高さと奥行きが1メートル強、幅が80センチメートルほどの装置の名前は「ウミトロンセル」。遠隔操作できる「スマート給餌機」だ。飼料を蓄えるタンクやカメラ、コンピューターなどが備わる。いけす内のデータを取得し、生産者に届ける。箱の上部の小型太陽光発電パネルで電力を賄う。アプリを用いて遠隔で餌やりのタイミングや量を設定し、食べているか確認できる。人工知能(AI)が魚の食欲を3段階で判定し、生産者は給餌を続けるか判断する。魚が餌を食べていない時はプッシュ通知で知らせ、餌の無駄と海洋汚染を防ぐ。餌やりは重労働だ。いけすとの往復や運搬の手間やコストが重い。ウミトロンセルは海が荒れて近づけない時も餌をやれる。技術開発には泥臭い努力の積み重ねがあった。リアス式海岸での養殖が盛んな愛媛県愛南町。18~19年度にわたりマダイ養殖で効果を検証した。藤原氏は養殖場近くに3カ月近く住み込み、社員も足しげく通い、生産者の声を基に改良を加えた。同社は藤原氏を筆頭に社員30人の約7割がエンジニアという技術者集団。佐藤彰子マネージャーは「養殖に特化し、改良と新機能の実装が素早いのが強み」と語る。感覚頼みで1日数回が限度だった餌やりを10回以上に分けて最適化でき、マダイが1キログラムまで成長する期間を4カ月短縮することに成功。餌も削減できた。現在は中四国や近畿を中心に数十社がレンタル利用する。「遠隔操作で海に出る負担が減った」「無駄が減った」と評判は上々だ。餌を巡る技術革新の波はやり方だけではなく原材料にも及ぶ。時代の潮流は「脱魚粉」だ。■魚向けの飼料、脱魚粉に動く世界で養殖生産量が伸び、日本水産油脂協会(東京・渋谷)は「飼料用の魚粉の需要は今後10年でさらに増える」と指摘する。価格は高騰傾向で不足も見込まれる。そもそも天然魚の枯渇対策のはずの養殖の餌に使うのは矛盾してしまう。飼料大手フィード・ワンは07年にいち早く魚粉比率を4割ほど減らした飼料を製品化した。魚粉の代わりには大豆かすなどの植物性たんぱく、添加する魚油の代替にはパーム油などを採用する。さらに魚粉依存度を下げる研究を進める。昆虫や菌類由来のたんぱく質を魚粉、藻類由来油を魚油のかわりに使うことを検討し、今はまだ高いコストの低減を探る。国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」の14番目に「海の豊かさを守ろう」という目標がある。商品の購入でSDGsを重んじる消費者が増えており、脱魚粉の達成度合いで養殖魚が選別される可能性がある。養殖スタートアップのFRDジャパン(さいたま市)は20年1月、養殖や加工、流通が環境に配慮して適切に管理されていることを示す国際認証「ASC認証」を取得した。ASCはオランダに本部がある非営利団体で、認証を取るには飼料原料のトレーサビリティー(生産履歴の追跡)や海洋資源への依存度低減が必要だ。約10種類の餌を使い分ける同社は魚粉比率を減らした。FRDジャパンは魚粉比率を減らした餌を使うなど環境配慮に努めている十河哲朗最高執行責任者(COO)は「持続可能な養殖場で育った魚を買うことが豊かな食と環境を残すことにつながる」と語る。実際、イオンやイトーヨーカ堂など小売り大手が認証を取った事業者の魚を積極的に取り扱い始めた。餌の与え方と原料に向き合って切磋琢磨(せっさたくま)することが、養殖の世界を量的にも質的にも次のステージに引き上げる。(企業報道部 古沢健)8月2日は土用の丑(うし)の日。ウナギが恋しくなる季節となった。数ある養殖魚のなかでも、日本の食文化を象徴するウナギは実は約99%が養殖物だ。ところが、養殖に必要な稚魚が減っており、満足に食べられなくなる日が来てもおかしくない。解決の切り札として、卵のふ化から人が手がける「完全養殖」の実用化に近畿大学水産研究所が乗り出した。日本の養殖技術をけん引してきた同研究所は専門家を招いて難関に挑む。紀伊半島のほぼ南端、和歌山県那智勝浦町に近大水産研浦神実験場がある。飼育室に円筒形の水槽(縦約75センチメートル、横約25センチメートル)が4つ並ぶ。目をこらすと透明で長細いニホンウナギの仔魚(しぎょ)が見える。仔魚は、稚魚の「シラスウナギ」になる前段階を指す。人工的にふ化させたもので、柳の葉のような形だ。体長は最大35ミリメートルほどで、数百匹が泳ぐ。田中秀樹教授は「早いもので11月ごろシラスウナギになる」と説明する。土用の丑の日などに親しまれるウナギの養殖は岐路に立つ。天然のニホンウナギは5~15年ほど日本の河川や河口域で暮らして海へ下り、約2千キロメートル南方のマリアナ諸島の西側海域で産卵。ふ化した仔魚が海流に運ばれて稚魚のシラスウナギとなり、日本列島などにやってくる。従来の養殖は5センチメートルほどのシラスウナギが海から川に上がろうと河口付近に集まったところを網で捕まえ養殖池で育てる。早ければ半年ほどで50センチメートル前後の成魚になる。今、養殖の要のシラスウナギの漁獲が安定せず不漁が目立つ。乱獲や環境変化が原因とされる。今年は豊漁といわれるが、最盛期の約半世紀前の10分の1ほどにすぎない。■卵から成魚まで、完全養殖で窮地を救う
窮地を救う技術と目されるのが完全養殖だ。卵を人工的にふ化させて成魚に育て、生まれた卵をまたふ化させて2代目を育む。天然の稚魚に頼らない人工飼育の循環だ。近大水産研には苦い経験がある。1980~90年代に採卵とふ化に成功したが、餌を食べず中断していた。その後、国立研究開発法人の水産研究・教育機構が2010年に完全養殖に成功した。近大水産研はそこで開発され、公表済みの技術をもとに研究を再開した。近大で研究を率いる田中教授は機構出身だ。約30年ウナギを研究し、完全養殖の成功に貢献。定年退職して18年に近大に移った。田中教授は「完全養殖はまだ実験室段階の技術」と強調する。機構を含め実用的な低コストで量産するめどは立っていない。「養殖に強い近大の知見も応用し、完全養殖を実用段階にする」ことがミッションだ。ウナギはいちから育てるのが難しい。仔魚を得る受精卵を生み出し、仔魚からシラスウナギにするのが至難の業だ。機構での成功体験を再現するだけでも「簡単ではなく、うまくいく時といかない時がある」。仔魚の生態は謎が多いうえ、飼育法が他の魚と違って特殊だけに設備や技術の再現が容易ではないのだ。まず手間がかかる。飼育環境下ではほとんどオスになってしまうため、採卵する母親候補にホルモン入りの特別な餌を与えメスにする。自然に起きない成熟を促すことも必要で、ホルモンを投与をして卵と精子を得る。人工授精で無事にふ化した仔魚もシラスウナギまで育つのは最大でも5%ほどだ。ネックは餌で、仔魚はほかの魚が口にする生きたプランクトンなどを食べない。■課題の餌、新たに開発
田中教授は機構時代、ウナギがなかなか餌を食べないことに悩んだ。成分や大きさを何度も変え、サメの卵などを使う餌を食べると突き止めた。ただサメの卵は成分や品質の変動が大きく、安定調達にも不安がある。近大ではサメの卵を使わず、酵素で処理して消化しやすい魚粉を含んだ餌を使う。新たな餌も開発していく。生育環境への目配りもカギを握る。水温は低いと成長が遅れ、高いと細菌が繁殖しやすいため、セ氏25度を保つ加温や冷却が必要だ。シラスウナギになってからも道のりは長い。かば焼き可能な成魚に育つのに実験室では早くて約1年、卵を産む循環を回すにはさらに時間を要する。25年ごろ完全養殖にめどをつけ、試験提供にこぎつけたい考え。実は今育てる仔魚は田中教授にとって近大では2度目の挑戦だ。初回の19年は最も長生きしたもので飼育期間は149日(最大37ミリメートル)で、そこで全滅してしまった。今回は成長差は大きいものの最も長いもので約100日を迎えた。田中教授は「まず完全養殖を再現する。それからよりよい餌の開発などで近大の知見を生かす」という。■近大の知見を生かす近大水産研でウナギの仔魚(しぎょ)を育てる水槽と田中教授(和歌山県那智勝浦町)
「海を耕す」との理念で1948年に誕生した近大水産研はブリなど18魚種で養殖のもとの種苗生産に世界で初めて成功した。2002年に成功したクロマグロの完全養殖も世界初の快挙だ。田中教授はこうした実績に期待する。近大が持つ養殖用飼料会社との太いパイプも生かせそうだ。とはいえ、他の魚と性質が大きく異なるウナギの完全養殖は、論文やデータベースをあたればたちどころに解決するような生易しいものではない。「むしろ文字や数字に表れない研究者の知見にヒントが隠されている」と考え、密なコミュニケーションを進めていく。ニホンウナギは絶滅危惧種でもあり、近大以外でも量産の研究が進む。田中教授の古巣の機構は量産に必要な餌や飼育システムの確立をめざす。東洋水産グループのいらご研究所(愛知県田原市)も研究を進めている。シラスウナギの減少には台湾や中国などアジアの国・地域も悩んでいる。食文化を守るためにも、完全養殖をはじめとする技術が果たす役割は大きい。(企業報道部 大林広樹)
・人手不足に悩む水産業に助っ人 AI・DXで「漁夫に利」
漁獲量の減少や人手不足に悩む水産業に、強力な助っ人が現れた。人工知能(AI)が魚の種類や品質を自動で仕分けたり、気象衛星でも観測できない海水温のデータを「見える化」したり、デジタル技術が水産業の現場の生産性改善を後押しする。熟練の勘をデジタル化し、漁獲から仕入れまで安定した魚の供給と保全につなげる。水産のデジタルトランスフォーメーション(DX)の現場を追った。宮城県気仙沼市の魚市場。海の漁師たちの活気とは対照的に、アーム型のロボットが黙々とベルトコンベヤー上に流れる魚を素早くつかみ、魚の種類別にトレーへ仕分けていた。東北大や民間企業の研究グループが2019年4月から始めたAIによる自動仕分けシステムの実証実験だ。22年3月までに漁港や市場での実用化を目指す。カメラが頭の向きやサイズの異なる魚を撮影すると、画像を読み取ったAIが1尾あたり約0.1秒で魚種や大きさ、脂の乗りを判別する。その後、ロボットが判別結果を基に種類ごとに分けた箱に選別する。市場に運ばれた魚は、鮮度を維持するために魚種別に作業員を配置し、素早く分別する必要がある。AIやロボットで作業を自動化すれば、人手不足を解消し、作業負担を減らせる。「将来的にAIによる判別結果を流通のデジタルデータ化に生かしたい」。プロジェクトに携わる東北大大学院工学研究科の鹿野満特任教授はこう話す。魚種や数量のほか、水揚げ日時や場所を一元化し、すし店や居酒屋などの買い手が閲覧できる仕組みを作る。魚の流通は仲買人の流通網に頼るのが現状で、漁業者も不特定多数の買い手と直接取引できるようになれば販路拡大につながる。「流通が少ない魚が広がるきっかけにもなり、漁業者の収益向上や資源の有効活用に貢献したい」(鹿野氏)と話す。スマートフォンを使って、水揚げした魚の品質判断ができる技術も導入が進む。電通などは、仕入れ時にマグロの品質を自動で判定するAIソフトを開発した。「TSUNA SCOPE(ツナスコープ)」というスマホアプリで、スマホのカメラでマグロの尾の断面を撮影すれば、AIが『おいしいマグロ』を瞬時に判別する。マグロは魚体ごとに鮮度や味が異なり、通常はベテランの目利き職人が尾の断面を見て、脂や身の収縮具合、赤身の色や艶から品質を判定する。AIは職人が目利きした結果と大量のマグロの尾の断面画像を蓄積する。品質は「A(最上級)」「B(上級)」「M(並品)」の3段階など使い手によるカスタマイズが可能で、9割の確率で正確に見分ける。中国・大連や静岡県焼津市などの水産加工場が導入した。ツナスコープは、職人の後継者不足という課題を解決する可能性がある。通常、目利き技術を培うためには、20年ほどの長い歳月がかかる。ツナスコープのプロジェクトリーダーを務めた電通の志村和広氏は「日本が育ててきた目利き技術を残すため、AIで職人の技術を保存・継承していきたい」と意気込む。■漁獲量は減少傾向、収益改善に向け生産性向上が喫緊の課題
国連の持続可能な開発目標(SDGs)の1つに「海の豊かさを守ろう」という目標がある。海洋資源を守りつつ、持続可能な形で利用することは、世界が達成すべき目標だ。農林水産省によると、19年の漁業・養殖業の国内生産量は前年比6%減の416万トンと減少傾向が続く。農水省は水産資源の維持と回復のため、サンマやクロマグロなど計8魚種で漁獲量を制限。今後、新たに15魚種の追加も検討する。漁師は漁獲量を制限された環境下で、燃料代などのコストを下げて利益を出す必要がある。京都大発ベンチャー、オーシャンアイズ(京都市)は、潮の流れや海水温のデータを推定する技術を開発し、漁師の抱える悩みの解決を試みる。多くの漁師は船上で、長年の経験や熟練の勘をもとに魚をとる漁場を決める。その際、潮の流れや海水温は重要な判断材料となる。しかし、衛星データの更新頻度が少なかったり、雲で隠れた部分の情報は取得できなかったりと最新の情報に頼れないのが現状だ。オーシャンアイズが開発した「漁業ナビ」は、AIなどが気象衛星のデータを基に海の表面温度や潮流の向き、強さを推定する。漁業ナビの情報を基に、魚を捕りやすい領域や網入れのタイミング決めに生かす。漁師は燃油代などのコストを抑え、収益を上げられる。気象衛星「ひまわり」が24時間365日観測するデータをAIで蓄積し、雲で隠れて観測できないエリアを補完する。温度を色で表した海水温図も作れる。さらにスーパーコンピューターを用いて、潮の流れを矢印で示した潮流図を作製し、1時間毎に最新のデータを提供する。海底までの水温のほか、最大2週間先の海況も約2キロメートル四方の解像度で予測し、将来の海況も予想できる。モニター上の海水温のデータは1時間ごとに更新され、漁師が漁場を決める判断材料となる同社の笠原秀一取締役は、「魚がどこにいるのかという手掛かりが増えれば、効率的に漁ができる」という。22年3月までに海外展開や遠洋漁業船への導入を視野に地球全体のカバーを目指しており、「収益の不安定さに悩む漁業者を支援しつつ、海の豊かさの維持に貢献したい」と話す。■AIで養殖魚の尾数を計測
養殖魚の生産現場でも人手不足や高齢化が進んでいる。マルハニチロやTokyo Artisan Intelligence(トウキョウ アーチザン インテリジェンス、横浜市)は20年4月から、AIでブリやカンパチの養殖魚の尾数を管理するシステムの運用を始めた。これまでは健康状態のチェックやいけすを移し替える際、カンパチとブリをあわせて年間1000万尾のカウント作業が生じていた。カメラで1秒間に数十枚の画像を撮影し、魚の特徴を学習したAIが動きの激しい魚の尾数を計測する。従業員の体力的な負担を軽減できるほか、計測作業をしていた2~3人分の労力を減らし、いけすの修繕などの他の作業に充てられ、生産性を高められた。養殖業の場合、エサ代はコストの5~6割を占める。養殖中の魚の数を正確に把握すれば、余分なエサを与えることを防げる。今後は、ブリやカンパチの稚魚や他の魚種にも対応していく。農林水産省によると、漁業の就業者数は10年に20万2880人だったが、19年には14万4740人と10年近くで3割減少した。現場の高齢化も進んでいる。漁夫の「利」となるDXは、水産業の足腰の強さを維持する切り札となる。(大阪経済部 丸山景子)【第3部 Coolに冷やす】冷凍パンでも出来たての風味を再現できる
日本で冷凍事業が始まって100年。進化を続ける冷凍・冷蔵技術が新たなビジネスを生み出している。冷凍しておいしさを保ったまま食品を届けるサービスや、食材を効率よく凍結させる機械など新たな製品も登場する。2020年の国内の冷凍食品市場は過去最大を更新する見込み。食品ロス問題の解決を後押しする「Coolテック」が熱を帯びてきた。
「冷凍パンはじめました」。東京さくらトラム(都電荒川線)の梶原駅を降りて商店街を3分ほど歩くと、冷凍パン専門店「パンフォーユー カジワラ」が見えてくる。空き店舗を改装した小さなパン店の店頭には、北海道から沖縄県まで地方のパン店から取り寄せた20種類のパンが並ぶ。
ただ、店内に入ってもパンの焼ける香ばしい香りは一切しない。パンは一つ一つ袋詰めされ、冷凍された状態で保管されている。食パンやあんパン、カレーパンにバゲットなど品ぞろえは様々だ。
店舗を運営するのはスタートアップのパンフォーユー(群馬県桐生市)だ。自宅に毎回違った店の数種類のパンを郵送する定額サービス「パンスク」も手がける。
■冷凍してもパン本来の芳醇な香り
記者も自然解凍したクロワッサンを食べてみると、外側はサクサク、中はふわふわで、ベーグルも袋を開けた瞬間、パンやごまの香ばしい香りが漂ってきた。
食感と香りの秘密は包装材にあった。袋は包装資材メーカーと共同で開発。密閉性が高く、酸化の原因となる酸素の透過を抑え、中にあるパンの水分は逃がさない。
一般にパンを冷凍すると、パンに含まれる水分が失われ、パン本来のモチモチとした食感を損ね、パサパサとした食感になってしまう。パン本来の芳醇(ほうじゅん)な香りは時間とともに消えて、パンの風味も落ちるという。パンフォーユーは独自の包装材で、水分やパンの芳醇な香り成分だけを閉じ込める。
冷凍のタイミングにも工夫がある。パン店には袋と冷凍方法を教えるビデオを配布。パンを焼き上げて店頭に並べる一番おいしいタイミングで袋に入れて冷凍する。ビデオでは「袋を閉じるときに空気を抜き過ぎないようにして、パンの香りも追い出さない」などの注意点も細かく指南する。一般の冷凍庫で問題なく冷凍できるという。
パンフォーユーが指南する方法で保存すれば、焼いてから30日後の冷凍パンが、常温で1日置いたパンよりモチモチとした食感で、水分量も多いという調査結果もある。
パンを提供する地方のパン店側の評判も上々だ。「ブーランジェリーサイ」(群馬県高崎市)の店主の斉藤貴規さん(41)は「全国のパン好きに届けることができて、商圏も広がった。安定収入につながるのが1番のメリット」と話す。
パンフォーユーの矢野健太社長は「冷凍パンを宅配するビジネスは海外でもほとんどない」と話す。同様のビジネスを海外展開してほしいというオファーもあり、世界に羽ばたく可能性も秘める。
■コロナ禍の外出自粛、Coolテックで食を豊かに
コロナ禍で外出自粛や在宅勤務が広がるなか、Coolテックは食の豊かさを家庭にもたらす技術としても注目される。
「冷凍とは思えないおいしさ」、「本当に冷凍ですか?」。健康食配達サービスのファンデリーの公式ツイッターには驚きのメッセージが数多く寄せられる。一般の消費者向けに総菜や弁当を宅配する「旬をすぐに」を7月に始めた。
ほぼ全ての食材で国産にこだわり、食材の旬に合わせて毎日メニューをつくる。「宅配食は参入も多いが、旬のおいしさを届けて差別化したい」(同社)という。そのおいしさを支えるのが「イータマックス冷凍システム」と呼ぶ冷凍技術だ。
同システムを使えば、冷媒を蒸発させる蒸発器と空気の温度差を小さくして運用でき、蒸発器に霜が付くのを防げる。霜が付かないため、冷却の効率が上がり、セ氏マイナス70度の低温状態で食材を一気に冷凍できる。
サービス開始に合わせ、69億円を投じて埼玉県本庄市に初の自社工場を1月に竣工し、同システムを用いた最新の冷凍設備も導入した。
冷凍する際、水の分子が集まった氷の結晶が表面で膨張して食材の細胞組織を破壊してしまう。解凍した場合にこうした水分が「ドリップ」として溶け出し、味や香りを損なう。氷の結晶が大きくなる前に急速冷凍すれば、おいしさを保ったまま出荷できるという。同社は「スイーツなどメニューを増やし認知度を向上したい」と意気込む。
■冷食市場の拡大、技術進化を促す
冷食の国内消費量は2019年に295万トンと過去最高を記録した。新型コロナウイルスによる影響で中食需要も高まり、20年には300万トンの突破も視野に入る。冷凍技術の進化が市場拡大を加速させている。
10月に開かれた展示会「冷食JAPAN」でひときわ人だかりができたブースがあった。ラベル用の粘着材料大手のリンテックだ。展示していたのは5月に発売したラベル素材「CHILL AT」。低温環境下でもラベルを貼り付けられる。
展示では氷水で冷やされたペットボトルを使ってCHILL ATの特徴を実演して説明した。シールはボトルについた結露をものともせず、しっかりとボトルにくっついた。一方、通常の粘着剤を使ったシールを貼り付けようとすると少し手でこするだけで、シールがはがれてしまった。
一般の粘着剤は低温下では硬くなってしまう。そのため、ボトルに付いた水分が邪魔をして粘着剤がボトルに届かず、すぐはがれてしまう。
そこでCHILL ATは米国子会社が開発した特殊な成分を配合した粘着剤を採用。低温下でも柔軟性を失わないため、粘着剤が対象物に付着した水分同士の隙間に入り込むことができ、水分があってもしっかりとラベルを貼れる。
マイナス5度でも冷凍食品などの製品パッケージに貼れて、マイナス80度の環境下でもはがれないという。「コロナ禍で冷食需要が拡大しており、冷食のラベルのニーズも高まる」(山本貴司市場開発室長)とみる。
冷凍技術の進歩は食品のおいしさを保つだけでなく、物流や食品ロスの削減などにも一役買う。国内の食品ロス量は612万トン(2017年度推計)で、そのうち、328万トンが食品関連の事業者から排出されたと見込まれる。新しいラベル素材のように、無駄を減らす技術開発が一段と求められる。
(企業報道部 逸見純也、古沢健)
セ氏マイナス30~35度に冷やす特殊冷凍で鮮度を封じ込める。冷凍技術は新型コロナウイルス禍で売り先を失ったり、自然災害で傷ついたりした青果物の救世主としても存在感を示している。特殊冷凍事業のデイブレイク(東京・品川)は冷凍果物の配達サービスを手がけるかたわら、地方企業への技術提供を始めた。捨てられるはずだった果物を長持ちさせる技術は、地域活性化と食品ロスの削減に貢献し、新たなビジネスのタネにもなっている。リンゴ、ナシ、イチゴ、ブドウ――。長野県南部の豊丘村にある冷凍カットフルーツ加工場。白い作業着姿の担当者が包丁でへたや傷などを取り除いてカットしている。そばには2台の急速冷凍機が並ぶ。四方から冷気が吹き出し、セ氏マイナス30~35度に冷やす。冷凍直後のイチゴは真っ赤な表面にうっすらと白い結晶がたくさんできているのがわかる。包装して冷凍庫で貯蔵する。■冷凍技術で「地域おこし」
果物は冷凍保存すると、風味や食感、色味が損なわれやすいが、ここでは3年以上保つことができる。解凍後もおいしく食べられ、凍結状態でもサクサクの食感だ。10月に本格稼働したばかりの加工場を運営する南信州クリエイション(同村)は4月に立ち上がった新興企業だ。「地域おこし協力隊」として来村した前田隆幸氏が定住のために起業し、社長を務めている。はじめから高品質品をつくれるのは、デイブレイクが支援しているからだ。適した冷凍機の選定を手伝い、冷凍ノウハウを惜しみなく提供した。完成した冷凍果物の販売も支え、デイブレイクの電子商取引(EC)サイトで今後扱う。高品質を3年以上保つ冷凍ノウハウと急速冷凍機(後ろ)を加工場に提供し、販売も支援(長野県豊丘村)デイブレイクは特殊冷凍機の専門商社として、機械の販売と導入支援を手がけてきた。機械はメーカーの市販品だ。デイブレイクの強みは、冷凍機の性能を最大限に引き出しながら、高い品質を実現させる独自の「使いこなし術」にある。同じ冷凍機でも使い方で味に差が出るのだ。勝負は冷凍の前から始まっている。果物が熟れた状態で適切な大きさに素早くカットする。木下昌之社長は「最もおいしい状態で『タイムカプセル』にのせるためだ」と表現する。マイナス35度にもなる急速冷凍は時間の設定や並べ方がカギとなる。果物により水分量などが異なり、固まるのにかかる時間は少しずつ違う。一度に入れすぎると温度が十分下がらず、中心部までしっかり固まらない。冷凍保管庫でも温度管理と包装の仕方がまずいと色や食味が劣化する。詳細は門外不出ながら、一連の工程のなかで劣化を防ぎ、おいしくするための条件を同社は知り尽くしている。それゆえ、変色を防ぐ褐変防止剤などの添加物は使わない。「食材ごとの細かい品質維持ノウハウは機械メーカーも持っていない」(木下社長)この技術を地域産品の価値向上に生かす場が加工場だ。「捨てられる無駄を価値に変える循環型経済をつくり、雇用を創出したい」と木下社長。総勢7人が働く南信州クリエイションの前田社長は「指導のおかげで質の高い商品が作れる。地域のイメージアップにつなげたい」と意気込む。木下社長は実家が冷凍機の設置や整備を手がけていたことから、冷凍に思い入れがあった。2013年にデイブレイクを創業する前、タイの露店で食べた果物のおいしさに感動し、日本でもこのままの鮮度で味わえないものかと思案した。デイブレイクの木下社長(中央)はさまざまな食材で冷凍データの収集を進める■食品ロス解決にも一役
一方、果物が大量に捨てられている実態にも心を痛めた。様々な食材で冷凍や解凍の実験を重ねてデータを取り、ノウハウを積み上げていった。19年春に規格外や傷ついた果物を冷凍加工して届けるサービス「HenoHeno(ヘノヘノ)」を始めた。原料は全国50超の生産者から買い取り、都内で加工してきた。だが物流費がかさみ、時間も要するので輸送中に傷むリスクがあった。生産者のそばに加工場を設ければ、コストを抑えて質の高い完成品を量産できる。地方企業と連携して3年で50カ所に増やす目標を掲げる。機械や技術を地域と共有する「シェアリングファクトリー」と位置づける。ヘノヘノは企業向けで累計200件に達した契約先で在宅勤務が広がった影響で、解約も出ている。その半面、一般向けはネット販売が巣ごもり需要で好調だ。コロナの余波で売り上げが減った観光農園などのイチゴやサクランボを積極的に冷凍加工したところ、「食べるだけで社会貢献になる」と人気を集めた。ヘノヘノに続いて始めたスムージー原料を含めて、カフェなど業務用の引き合いも多い。加工場網は安定供給に役立つ。冷凍技術を果物向けにとどめるつもりはない。解凍の方法に至るまでさらなる研究を進め、野菜や肉、魚といった幅広い生鮮品を売りたい生産者と、高品質で長期保存できる冷凍品がほしい事業者を結びつけて技術で支援していく考え。「あの時、あの場所で、あの人と食べた味が忘れられない」。木下社長はこんな体験を増やすために走り続ける。(企業報道部 大林広樹)
・急冷・小型化、コロナ禍で急増の冷食 新技術に磨き新型コロナウイルスの感染拡大で外出自粛や在宅勤務が増えるなか、脚光を浴びる冷凍食品。保存ができて手軽に調理できることから需要は右肩上がりで増え続けている。冷凍機器や冷凍庫メーカーもこの商機を逃すまいと冷凍技術を磨き、勝負をかけている。10月上旬、新型コロナ禍にもかかわらず、東京ビッグサイト(東京・江東)には3日間で延べ2万8000人の来場者がつめかけた。食にまつわる展示会「FOOD展2020」で、特に注目されたのが、初めて開かれた「冷食JAPAN2020」だった。入場ゲートをくぐると、ひときわ目を引いたのが冷凍機メーカー、タカハシガリレイが展示した急速冷凍機器の「超小型L字形フリーザー」だった。冷凍食品を大量に生産するため、食品メーカーはトンネル状の冷凍装置を使った「トンネルフリーザー」を使うことが多い。タカハシガリレイはトンネルフリーザーの業界最大手で、その登録商標を持つ。■トンネルフリーザーを小型に食品をベルトコンベヤーで運びながら、機械の内部でセ氏マイナス35度の冷風を吹き付けて急速冷凍する。大量生産が可能な一方、コンベヤーで運びながら冷却するという構造のため、広いスペースも必要だった。そこで同社は機器内部で食品に吹き付ける冷風の強さを秒速5~6メートルから秒速18メートルまで引き上げ、さらにコンベヤーの上下のノズルから風が吹き出し、2方向から冷やすように設計を工夫した。強い冷風で食品の表面の温度層を壊しながら急速冷凍する。その結果、通常の2倍の早さで冷やせるようになり、これまで最も小さかった製品よりもさらに設置面積が半分のサイズまで小型化に成功した。山森悠示主任は「今あるスペースを使って冷食を作りたいという需要は大きい」と話す。冷食の需要が高まり、これまで冷蔵の商品を作っていた企業が新事業として導入を検討する事例が増えているという。タカハシガリレイはトンネルフリーザーを従来製品の2分の1まで小型化した三菱重工冷熱も小型化ニーズに応えた自然冷媒冷却設備を展示した。環境負荷の低い二酸化炭素(CO2)やアンモニアを冷媒に使用。見た目はまるで小さな物置のようだ。設置面積は従来品より31%減、重量も27%減の3トンまで減らした。荷物搬入用のエレベーターを使って運べるという。日本や欧州では2016年に改正されたモントリオール議定書を受け、冷蔵・冷凍倉庫や凍結設備に使われてきた冷媒をR-22冷媒(フロン)から環境負荷の低い自然冷媒への切り替えが進んでいる。「今後、中小規模の倉庫の更新需要に備えて提案していきたい」(同社)と意気込む。産業用冷凍機大手の前川製作所は冷蔵帯専用の冷却装置を売り込む。構造はトンネルフリーザーと同じく、コンベヤーで食品を運びながら冷風を吹きかけて冷やす。新製品はコンピューターによる気流解析(CFD)を繰り返し、送風ファンなどの配置を改善した。上部から吹く冷風が均一に行き渡るように工夫した。従来は送風ファンやクーラーの位置によって冷却にムラが発生することもあった。食品を冷やす場合、規定の温度以下まで冷やすため、冷却ムラによって冷蔵帯の食品でも冷やしすぎて凍結してしまう恐れもあった。「食品は素早く冷やさなければ、菌が繁殖して味も落ちてしまう」(同社)と話す。ムラなく冷やすことで食品のおいしさを保ったまま出荷できる。コンビニエンスストア向けに弁当や総菜を供給する食品メーカーの需要を見込んでいるという。■Coolテック、iPS細胞の研究にも応用
大手のメーカーが冷凍技術を競う一方、独自の技術で存在感を高めるメーカーもある。「急速冷凍を競う時代はもう終わった」。冷凍・凍結装置製造のアビー(千葉県流山市)の大和田哲男社長はこう話す。アビーの武器は大和田社長が発明した「セル・アライブ・システム(CAS)」という冷凍システムだ。CASエンジンと呼ぶ装置を冷凍機に取り付け、凍結機のなかに磁界を発生させる。すると微弱な電流が素材に含まれる水の分子を振動させ、氷の成長を抑え、その後瞬時に冷凍させることによって細胞を壊さずに凍らせることができる。解凍後に水分がドリップとして流れ出てうまみを損なうこともない。実際にCASを使って凍らせた数年前の生しらすを記者が試食してみた。新鮮な生しらすとほとんど味も変わらず、見た目も水分が溶け出している様子はなかった。アビーのCASを使えば鮮度を大幅に保ったまま冷凍できる魚や肉のほか、調理済みの食品や野菜、果物でも同様に凍らせることができる。既存の冷凍機に装置を取り付けるだけなのでコストも抑えられる。海外や飲食店の引き合いが絶えないという。アビーの技術力は医療分野でも応用されている。京都大学の山中伸弥教授が所長を務める京都大学iPS細胞研究所(京都市)。iPS細胞研究の最先端でCASが活用されている。山中教授とiPS細胞の研究を進める長船健二教授と連携し、研究所にCASを使った冷凍庫を4台導入する。CASエンジンを取り付けた冷凍庫ならば、iPS細胞を使った組織を超低温ではない温度でも細胞を壊さず保存できる。今後数年間で保存に最適な温度帯や解凍装置などの研究を進める方針だ。冷凍・冷蔵技術の先進国ともいえる日本。分野や国をまたぎ、Coolに冷やす技術が世界を席巻する日が近いうちに訪れるかもしれない。(企業報道部 逸見純也)
養殖しやすいサーモンは、人口増に伴う食糧危機に対抗する切り札の一つになる、と食品業界ではかねて評されでいる。畜産は飼料として膨大な穀物を使い、家畜が排出するメタンガスは地球温暖化の原因となる。その点、魚類は環境負荷が小さく、人工肉や培養肉の技術と並んで期待が大きい。
しかし、海での養殖は世界的に適地が不足している。年間を適して低水温で、波が穏やかな深い入り江というのがサーモン養殖の条件だが、それを満たすのはノルウェーとチリのフィヨルドくらいしかない。そして、両国の養殖適地はすでに利用し尽くされている。おまけにノルウェーとチリは大消費地のアジアから遠く、輸送コストが大きい。
そこで期待されるのが、陸上でサーモンの陸上養殖施設だが、現在国内に続々と工場が建設されている。引用記事のFRDジャパンを遥かに上回る大規模のア′トランティツクサーモンの陸上養殖システムをソウルオブジャパン社が建設し始めた。
シンガポールに設立された世界的養殖企業の日本法人ソウルオブジャパン(東京・渋谷)が三重県津市で建屋の面積は6万7000㎡と、東京ドームの1.5倍の広さの施設を建設している。完成は2023年の予定。円筒状の水槽を36基設置し、その容積は8万~10万m3に達する。水道水からつくった人工海水をバクテリアでろ過しながら循環させ、アトランティツクサーモンを育てる。商業スケールでの陸上養殖システムではアジア最大級で、完成すれば年間1万トンのサーモンを供給する一大拠点となる。
元々は2018年、ポーランドで、陸上養殖に初めて成功した。現在、日本と米国、フランスの3カ国で養殖施設のプロジェクトが動いている。日本が建設で先行しており、2019年には伊藤忠商事と日本国内の販売が本格化する。
陸上養殖施設は消費地に近く、国内生産した新鮮な商品は、刺身としてこれまでのサーモンの概念を覆すらしく、温暖化による漁獲量の減少が、逆に食の質が向上する怪我の功名となる好例だ。
人口肉の現状
主要な穀物は当面、需給のバランスを保つとみられる。ただ、その多くを飼料用が占める。人口増で不足するタンパク質を増産しようとすれば主たるカロリー源である穀物の食用分を減らしてしまう。
欧州の一部ではコオロギとか昆虫を食用にし未来のタンパク質源という動きがあるが、我々日本人には勘弁してほしい。
欧州の一部ではコオロギとか昆虫を食用にし未来のタンパク質源という動きがあるが、我々日本人には勘弁してほしい。
日本では古くから精進料理など大豆など高タンパクの農作物を使った疑似的な肉を生産してきた。近年豆腐によるタンパク質補給等、植物由来のタンパク質すら使わない代替肉が登場している。
更に技術は進化し、オランダのマーストリヒト大学で医学・生理学の教授を務めるマーク・ポスト博士が、2013年世界で初めて細胞培養した肉の開発に成功した。
ポスト博士は2016年に共同創業者としてモサ・ミートを設立し、22年には培養肉を製品化する計画を練っているが、モサ・ミートがつくるのはミンチ肉だ。だが、日清食品はステーキ肉の人工培養に取り組んでいる。
日清が牛の細胞から培養するのは高級和牛のステーキ肉。2017年から東京大学の竹内昌治教授と共同で手掛け、既に1cm四方の培養肉の開発に成功している。日清食品では「25年3月までには7cm四方で厚さ2cmのステーキ肉の生産を目指す」とのことだ。
日本の食肉の売上高の大半をブロック肉が占めており筋組織の塊を肥育できれば将来、流通の幅が一気に広がる、と日清HDはみている。
培養ステーキ肉は牛から採取した細胞を培養して増やす。そして、増えた細胞を鋳型のようなシャーレに置いて、筋肉のもととなる厚さ2mmのフイルムのような薄い筋芽細胞モジュールをつくる。これを培養液の中で積層し、筋線経に近い肉の塊にしていく。
筋細胞が一方向に並んだ「配向筋組織」を形成すると、かみ応えのある培養ステーキ肉が完成するという。現時点では1cm四方の培養肉をつくるのに1週間が必要だが、将来はクリーンルームで自動生産できるようにする予定だ。
現在イズの大型化を進めると同時に、味も課題となる。より本物に近づけるため、脂肪や血液成分などをどのように加えるかの研究も進んでいる。
建屋の中で原材科をつくる先例となっているのが、LEDを使って野菜を育てる植物工場。日本では1970年代から研究となってはいたが、今のととろ建屋や設備の投資がかさみ、採算に乗りにくい。2019年度の国内市場は84億円と、わずかな規模にとどまっていた。
それがここにきて広く定着する兆しが見えてきた。1kg当たりの取引価格は800~1000円と露地栽培の3倍ほどのコストがかかるが、安定供給が確保されているうえ、異物が混入していないので食品加工に使うと検査の手問が省けるコンビニのサンドイッチ用野菜の供給源として定着しはじめた。
建屋をつくる工場ほど大げさな仕掛けではないが、個人農家規模で導入できるテクノロジーで農作物の生産力を引き上げるスマート農業と呼ばれる分野で、日本の大手企業が次々に参入してきている。温室ハウスに機器を張り巡らして収量や品質を高める。各社は日本が得意とする工業用制御の技術を農業生産に生かそうとしている。
オムロンは中国江蘇省の無錫市で、果物や野菜などを生産する実証実験を続けている。日照量、温湿度、二酸化炭素(CO2)量を自動で計測。ハウスの窓の開閉や太陽光の遮断、かん水、CO2の管理をし、農作物の潜在力を最大限に引き出す。「糖度を高める栽培も可能」という。
プラント建設のJFEエンジニアリングは14年から北海道苫小牧市などに生産工場を構え、トマトなどの作物を育成してきた。
JFEエンジは、ロシア・モスクワ近郊で人気の日本生まれのイチゴを生産する大規模工場の建設プロジェクトも手掛けている。
JFEエンジは、ロシア・モスクワ近郊で人気の日本生まれのイチゴを生産する大規模工場の建設プロジェクトも手掛けている。
今後は、中東などでも日本製植物工場プラント進出がを本格化する予定だ。温室の水耕栽培は水を循環させるため、「基本的に少量の水でつくることができる」。乾燥地帯ににこそ植物工場は向いている。
自動車部品大手のデンソーも浅井農園(津市)と共同でハウス農場を運営している。
デンソーが開発した自動収穫ロボット「RARO(ファロ)」は、車るで生き物のように動く。搭載カメラで赤く成熟したトマトの房だけを選別しロボットアームに取り付けたハサミで器用に摘み取る。
露地栽培は天候に左右されるのみならず、次第に土地が痩せていく。食糧安全保障の観点から考えれば、世界の農業は屋内型の施設栽培に移行せざるを得ない。
日本は、培養肉で日清食品HDのようなフロントランナーが存在し、食品バイオテクノロジーのスタートアップも次々に生まれている。
食料を生み出すフードテック、アグリテックは日本だけではなく世界の潮流でもある。
欧米では食と農林水産業に対する投資が盛り上がり、米IT大手も注目している。
欧米では食と農林水産業に対する投資が盛り上がり、米IT大手も注目している。
例えば米GV(旧グーグル・ベンチャーズ)は、北米で農家向け電子商取引(EC)サイトを展開するファーマーズ・ビジネス・ネットワークに出資しでいる。アマゾン・ドットコムは食品スーパーのアマゾン・フレッシュを通じて食品の知見を積み上げている。
前述したモサ・ミートのマーク・ポスト博士が13年に培養肉でハンバーガーを試作した際の資金はグーグルの共同創業者セルゲイ・プリン氏が提供した。“新しい肉”を研究するスタートアップには、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏も資金を投じる。言うまでもなく彼らの目利きは厳しい。着目するのは、商品やサービスが世の中の課題の解決につながるかどうかだ。
こうした食ビジネスに期待するマネーを受け、米国で注目すべきネタートアップが次々に誕生している。例えば世界で初めてクロマグロの細胞培養に成功した米シリコンバレーのフィンレス・フーズ。23年ごろに培養マグロ肉による刺し身の提供を目指す、サーモンの細胞培養も計画しているという。
商業ベースに乗せるフードテックの国際競争は、数年後には激しくなるとみられている。
フードテックは観光に代わる日本の再成長産業の核とすべきだ!
環境問題、しいては食糧問題は、人口100億目前の地球にとって非常に大きな問題だ。
中国など多くの国家が利己的な姿勢を強めており、食料のいつどこで広がってもおかしくない。習氏の振る舞いは、食糧の確保が国際関係次第で不安定になりかねないという世界の実情を映している。
日本はグローバルサプライチェーンが進化する恩恵を受けて食卓を豊かにしてきた。農林水産省の発表によれば、2018年度の日本の食料自給率は37%(カロリーベースによる試算)と過去最低を記録した。これをおおまかに解釈すれば、日本で食べられているもののうち、37%が国内で生産されたもので、残りの63%は海外からの輸入に頼っているということになる。
大規模な気候変動が起きなくても、食料の多くを輸入に頼っている日本は、食料問題は常に潜在的安全保障上の脅威となっている。
国際情勢は年を追うごとに不透明になっているのに、食料自給を現状のまま放置していいはずはない。従来の農業や畜産だけでは限界がある。食糧安全保障の観点から、企業が積極的に世界的に競争力がある。
また、世界的に人気が高まる日本食だが、その材料となる日本製食材は高級品として世界的に認知されている。現在自動者(ガソリン車)生産が日本の主力産業として、2019年-2020年の日本の自動車業界の業界規模(主要対象企業9社の売上高の合計)は65兆7,148億円となっています。多くの雇用と経済を支えている。しかし教条的な二酸化炭素排出ゼロの世界的に誤った潮流により、今後自動車産業は日本を支える屋台骨としていられるかどうか確実ではない。
もし、自動車産業に代わる日本を支える主要産業候補として、新しいフードテック技術(食料生産)やサービスの開発により、世界で年間売上高で700兆円の新産業が生まれる余地がある。食は人口増加によって需要が生まれる確実な感度産業だ。ここにイノベーションを持ち込めば、勝機は得られる。
日本企業の現場は食を生む技術の蓄積が進んでおり、今後の主力事業と位置付ける動きは広がるだろう。食料事業に活路を見いだす取り組みは、一企業のビジネスというだけにとどまらない。それは日本の安全を確保し、懸念が拭えない世界の危機を救うことにもつながる。
2050年日本のフードテック技術が人口100億人に達した人類の未来と地球を救うことになるであろう。



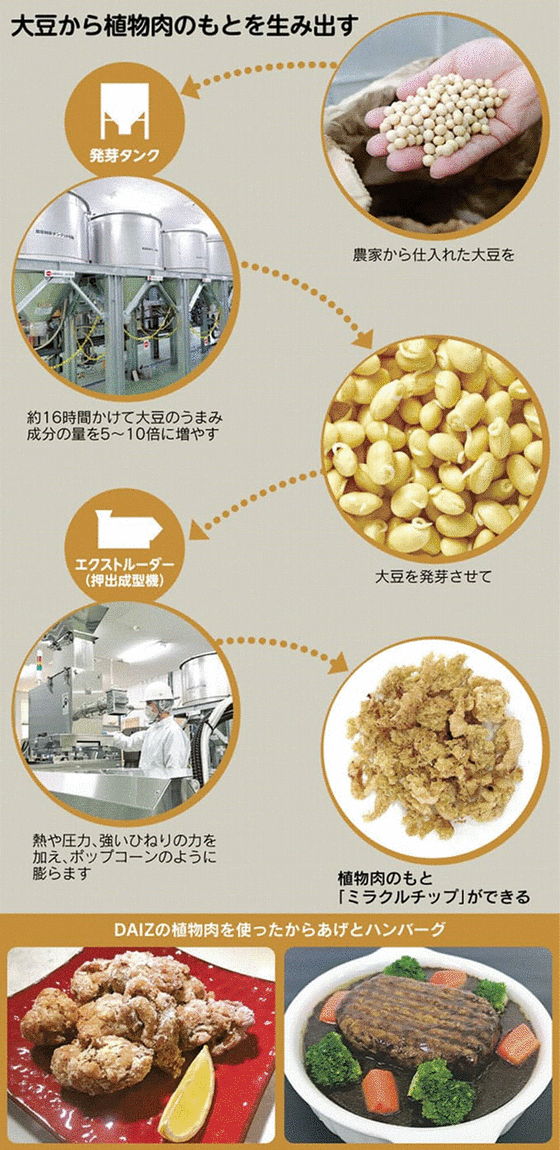
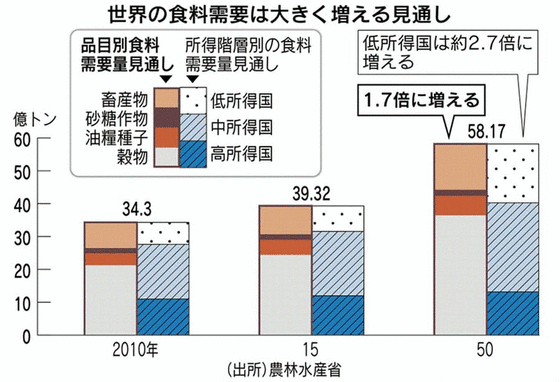
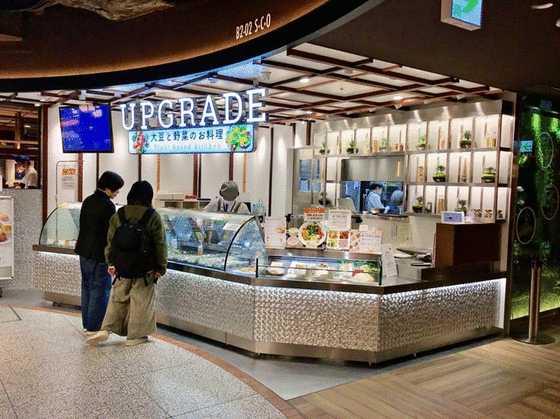


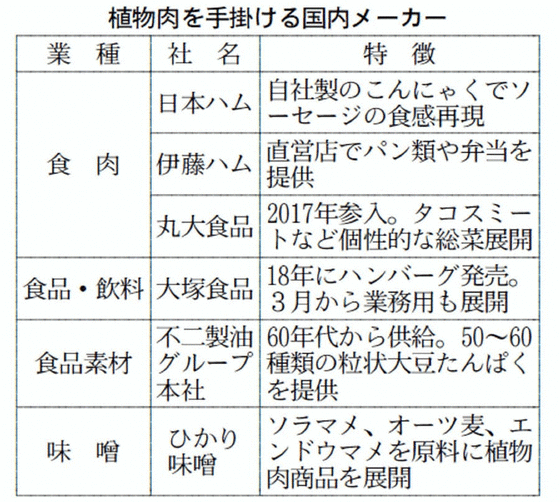
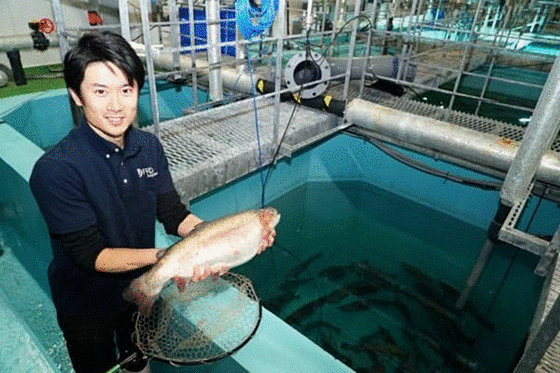
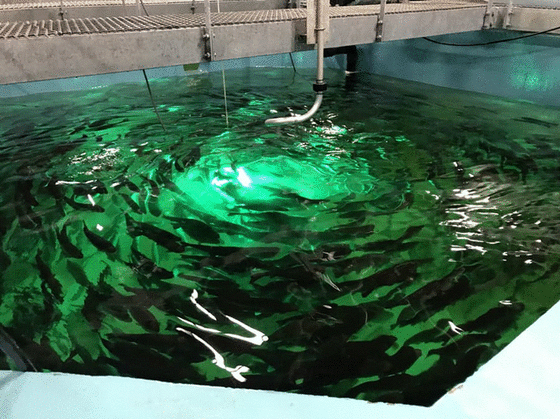
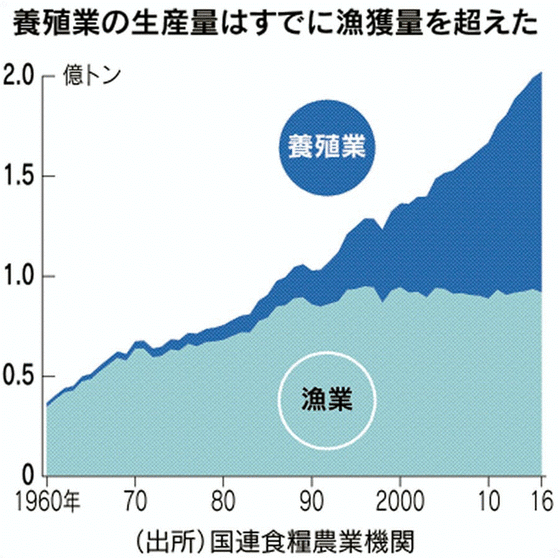
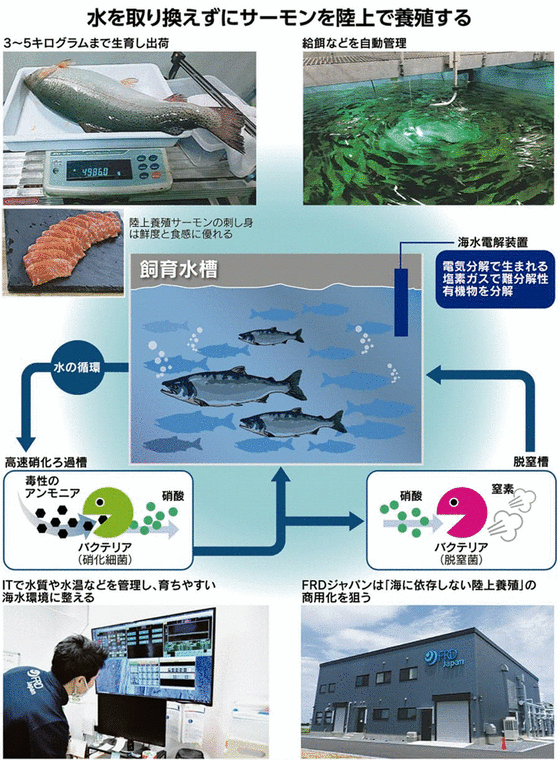

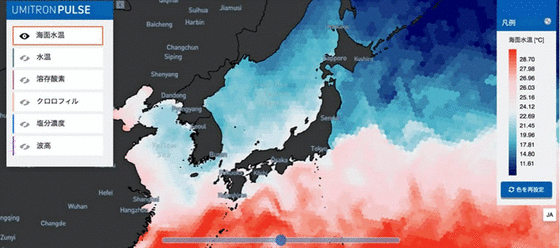
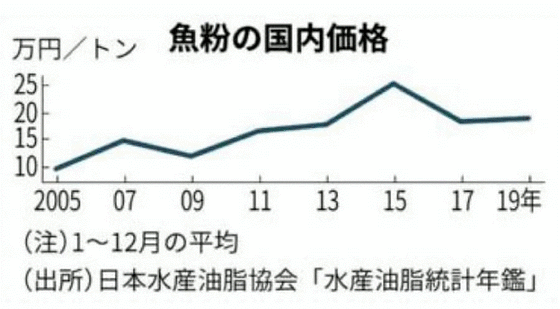

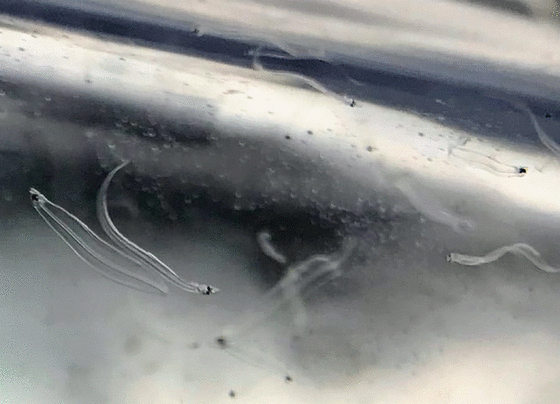
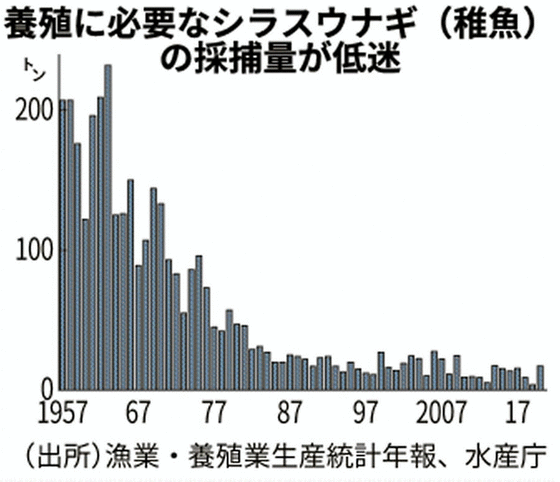
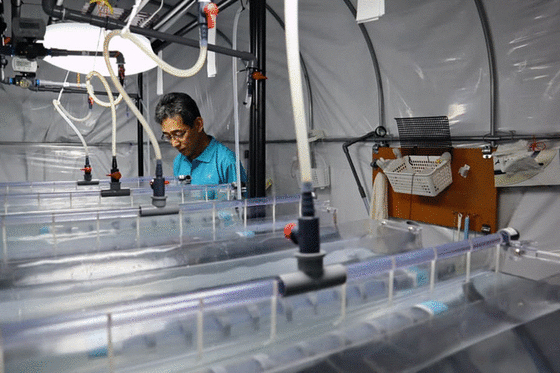

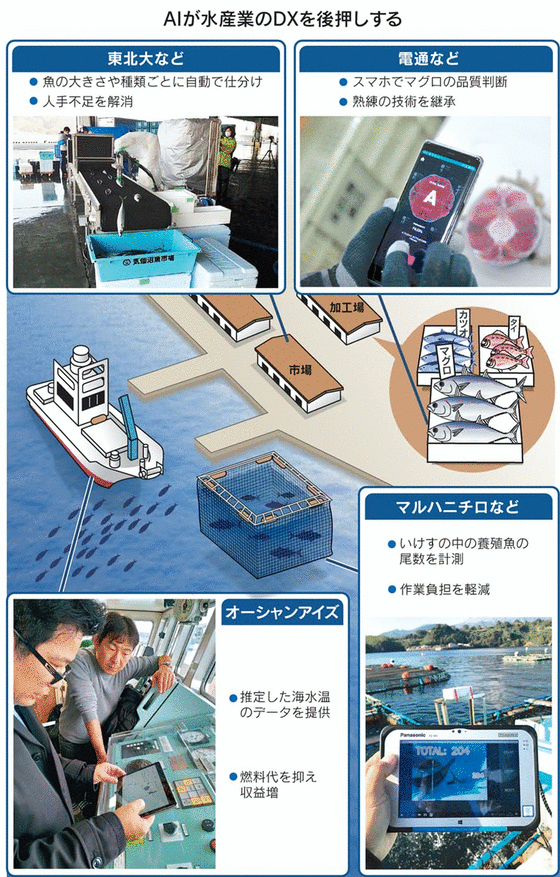
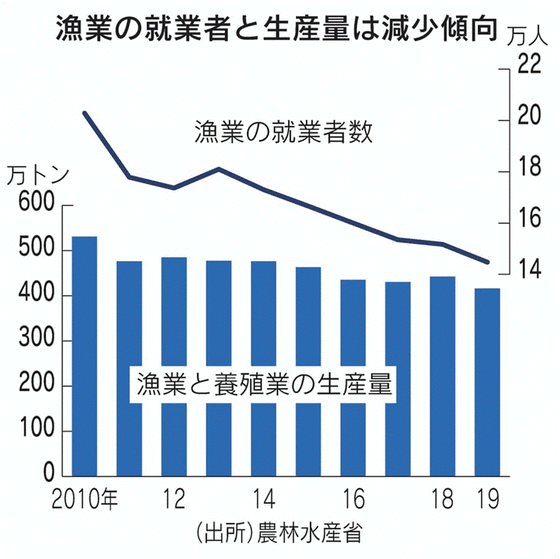
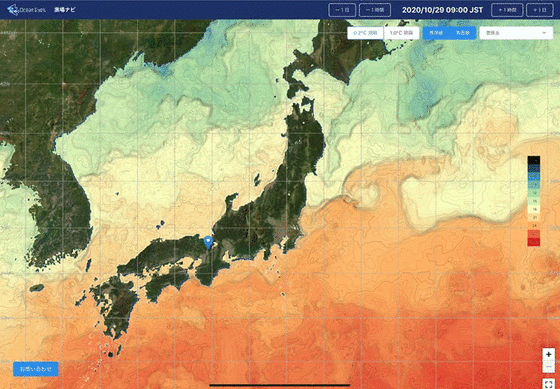






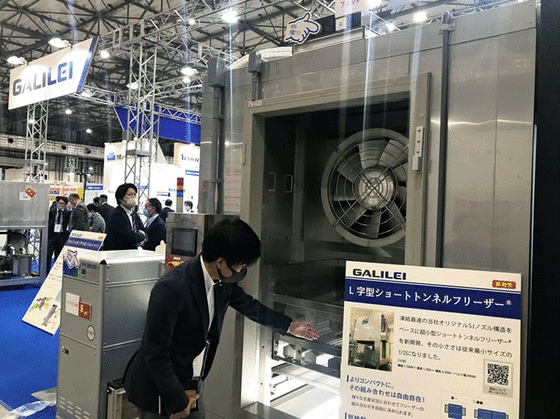
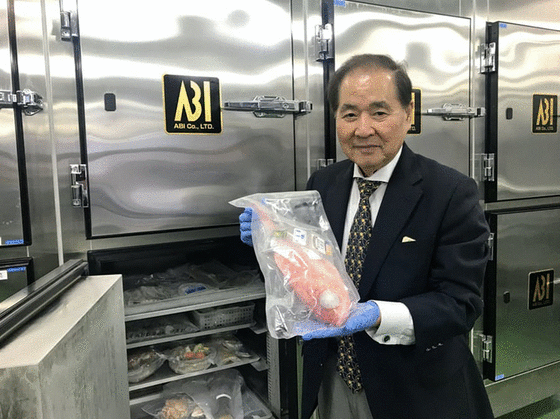





コメント
コメント一覧 (2)
軍事記事目的で時々楽しく拝見していますが、
コメントを書くのは初めてです。
今回の記事はボリュームがあり、読み応えのある良い記事でした、
コロナと少子高齢化で活気が無い日本ですが、
記事中でもあるように、
国内の環境技術と自動車産業のノウハウを活かせば新しい雇用を生み、
世界規模のシェアを十分に狙え、これからの地球環境を考えれば
絶対に必要な事だと思います。
これは日本の日本人でしか出来ない偉業だと思うので、
今までのように周りのバカな国に技術を盗まれないチャンスであり、
国産学でスクラムを組み日本の強みを活かして早く行動を起こしてほしいものです。
個人的にこのような記事もこれから話題にしていただけたらうれしいです。
Ddog
が しました
しました