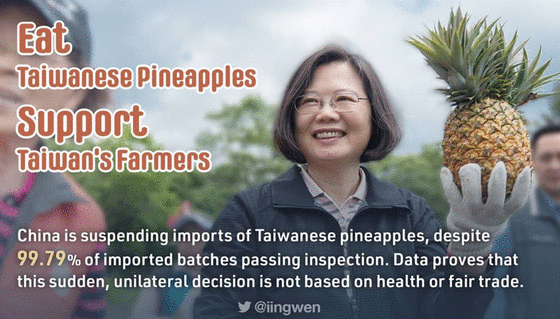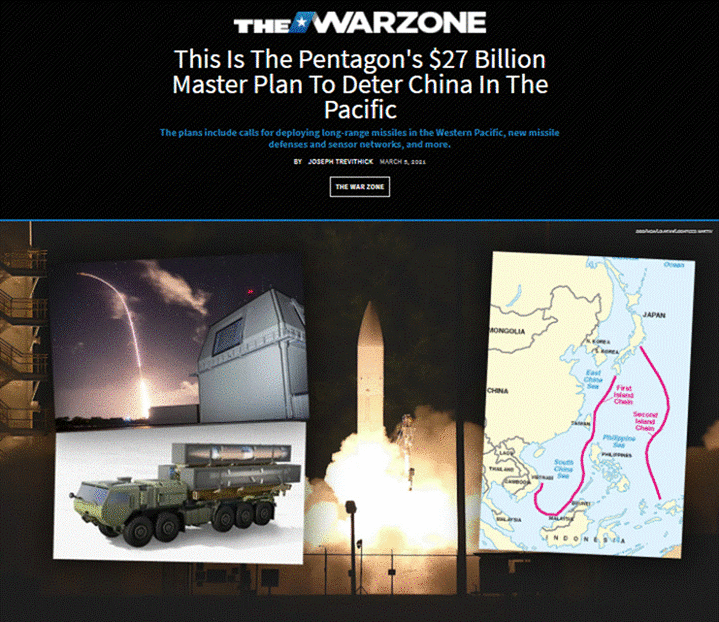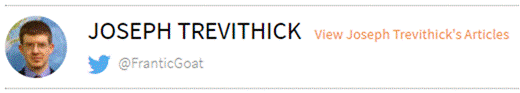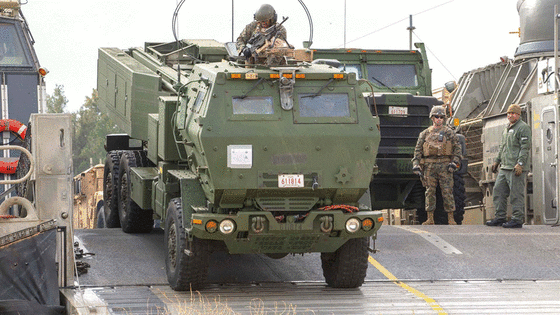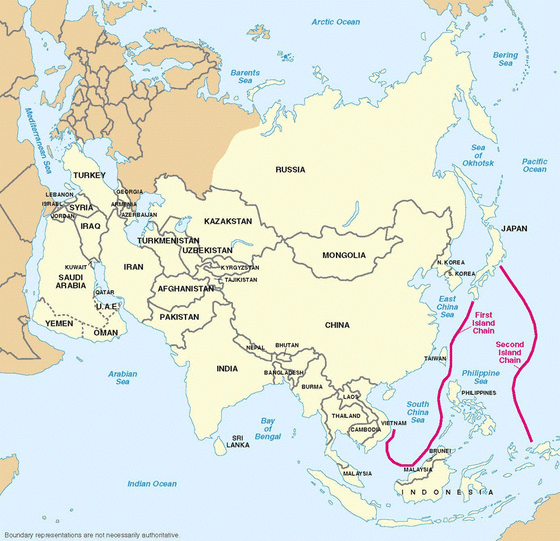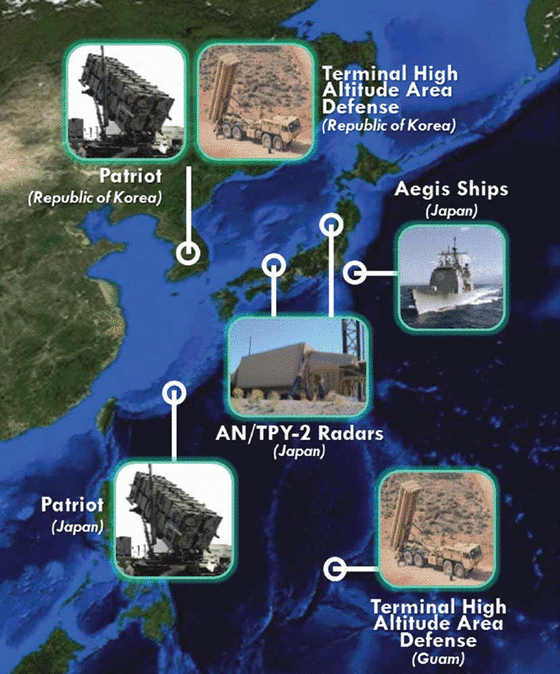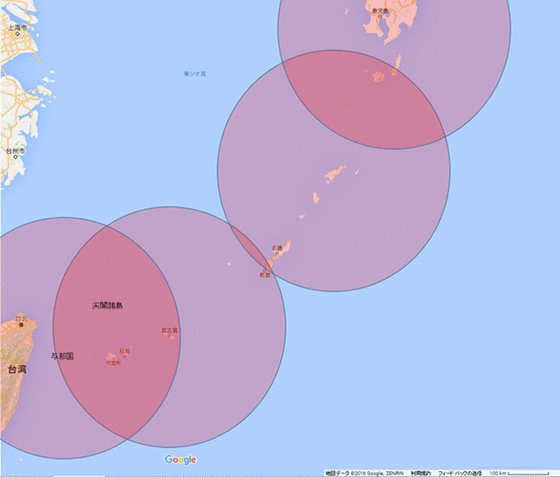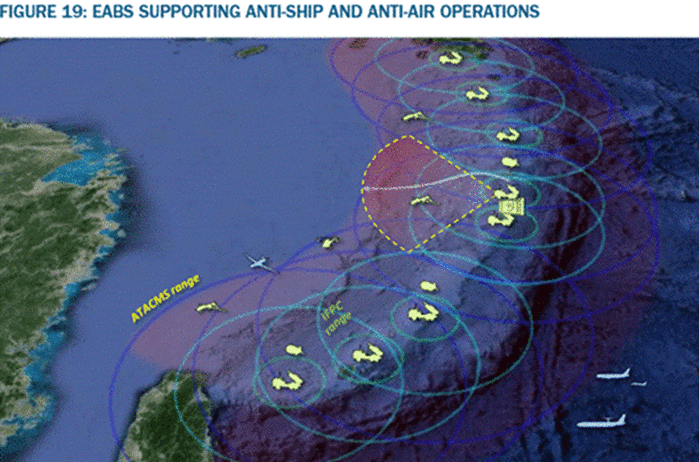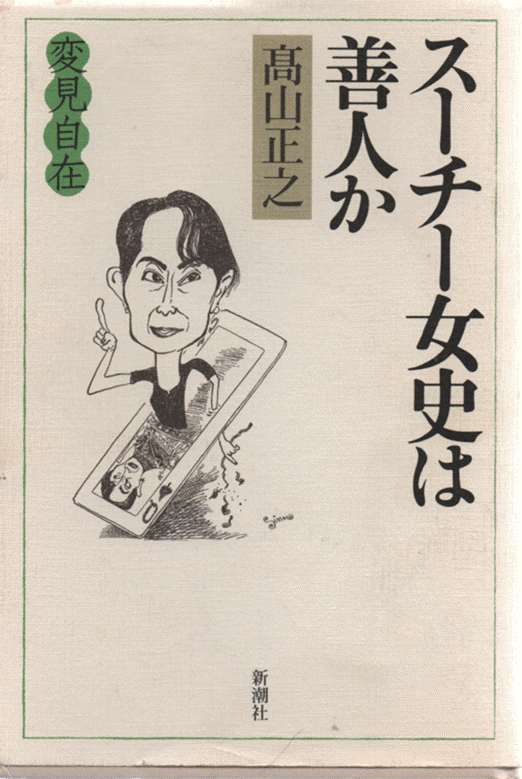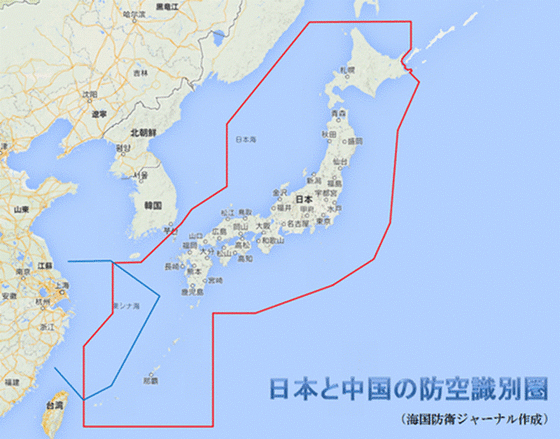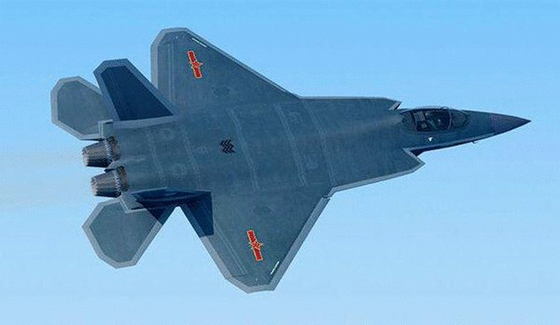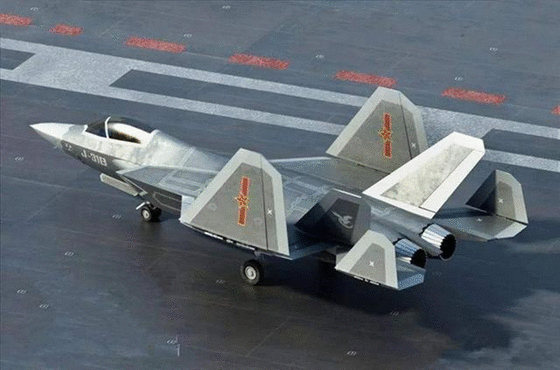デイリー情報を流します。私が毎日チェックしているYouTube等で、皆さんも見ましたか?役立ちそうですという情報番組を紹介しコメントします。
髙橋洋一728回 白川が黒田金融緩和政策を批判?白黒ハッキリついてますけど
FRB・米財務省・FDICが預金全額保護発表でも安心出来ない理由!!シグネチャー銀行もシリコンバレー銀行に続き破綻!アメリカ発の金融危
髙橋洋一728回 白川が黒田金融緩和政策を批判?白黒ハッキリついてますけど
03-13 今までの米国批判とは異なるレベルに突入
FT紙の米国による「封じ込め」、中国の訴えは正しいを読み私の意見を述べる。
FT紙の米国による「封じ込め」、中国の訴えは正しいを読み私の意見を述べる。
もし台湾が存在していなかったとしても、対立していたかという問いを記事では問うているが、即答で、私は米国と中国はやはり対立していただろうと思う。
覇権国が絶えず新興勢力と敵対してきたのは人類史の流れだからである。
仮に中国が中共の一党独裁国家ではなく民主国家だったとしても、大して変わらなかったろう。
中国の政府が選挙で選ばれたものだとしても80年代日本が潰されたように米国は中国を潰しにかかる。
国民性というものは簡単には変わらない。中国は中華思想国であり、中国以外は野蛮人であると考えている。西洋に辱められた時代ですら世界の中心だと思っていた。
覇権国になった米国は、常に倒すべき敵国を必要とする危険な国だ。どちらも自分ルール通りに行動している。
米中紛争は不可避だ。
中国の習近平は、中国の「封じ込め」「包囲」「抑圧」の背後にいるのは米国だと名指ししてしまった。
挑発的な発言だったが、厳密に言えば間違ってはいない。
ワシントンのコンセンサスは反中国っであり、中国に手を差し伸べる行為は全て悪と見なされる。
共和党民主党にかかわらず超党派のコンセンサスとなっている。
連邦議会下院に新たに設けられた中国特別委員会も超党派で、マイク・ギャラガー委員長は、「中国共産党のテクノ全体主義国家と自由世界との違いを際立たせる」と述べている。
中国に寛容だった欧米諸国は中国による世界侵略を暴いたベストセラー「サイレントインベイジョン」で驚き一気に反中国反中共となった
元祖の冷戦との大きな違いのはずだった、「ソ連と違って中国は革命を輸出してい」が間違いで「むしろより悪質国家」だと気が付いた。
1947年にジョージ・ケナンがフォーリン・アフェアーズ誌への寄稿「ソ連の行動の源泉」で打ち出した最初の「封じ込め」の概念は、今日の米国が公言せずに行っている封じ込めよりも穏健だった。
ケナンのアドバイスは、ソビエト帝国の拡張に歯止めをかけよ、そして西側の民主主義を強化せよという2本の柱でできていた。
武力は行使しないよう進言していた。我慢強さと技能をもって相対すれば、ソ連がいずれ倒れると書いた。実際、その通りになった。
今日のアプローチは「封じ込め+(プラス)」だ。
習氏が「抑圧」と言う時、それは米国が最先端の半導体の対中輸出を禁じていることを意味する。
米中経済のデカップリングは必然性を帯びてきている。
最先端の半導体は民生と軍事目的の双方で使われるため、米国側には、中国に軍備改良の手段を使わせない根拠がある。
習近平は、中国政府の目標は2030年までに人工知能(AI)を支配することだと明言している。これは中国がルールを定めたいという考えを表す別の言い方だ。
それゆえ、元祖冷戦に比べた場合の今日の冷戦は中国と米国の経済的な相互依存を解消米中経済のデカップリングから行わなければならない。
習近平は「包囲」に言及する時、中国の近隣諸国と米国が結びつきを深めていることに危機感を感じている。
ここでも、ほとんどは習近平自身に非がある。
中国が最も懸念しているのは経済包囲網が軍事的包囲網に発展することだ。普通に軍事的包囲網にシフトするだろう。
米国がフィリピンやインドに接近し、そして原子力潜水艦をめぐるオーストラリアや英国との安全保障の枠組み「AUKUS(オーカス)」の存在もある。
ここに米軍から台湾への武器供与の増加を加えると、中国は臨戦態勢となる。
今こそ米ソ冷戦を第三次世界大戦にしなかったケナンの封じ込め戦略が説得力持つ
切り札はまだ米国の方が多い。
同盟国がたくさんある。
自分で設計したグローバルな制度もある。
強豪国中国の指導者が愚か者の習近平である!しかも国を最貧国に陥れた毛沢東に憧れる独裁者である。ただ、米国の大統領もバイデンであり、こちらも習近平に劣らず愚か者だ、ただし、独裁者ではないぶん米国に利がある。
同盟国がたくさんある。
自分で設計したグローバルな制度もある。
強豪国中国の指導者が愚か者の習近平である!しかも国を最貧国に陥れた毛沢東に憧れる独裁者である。ただ、米国の大統領もバイデンであり、こちらも習近平に劣らず愚か者だ、ただし、独裁者ではないぶん米国に利がある。
米国は技術で中国より優れており、人口動態も若い。片や中国では経済成長が減速しており、社会の高齢化のペースも米国を上回る。
米国は決意と忍耐を持って臨むべきだという主張には、ケナンが活躍していた米ソ冷戦時代よりも説得力がある。
IMFがロシアの統計を信じない➡IMFが中国の統計も信じない
イーロン・マスクが1月6日のチャンスリーの釈放を訴え:
— 及川幸久 YUKI OIKAWA💎 (@oikawa_yukihisa) March 12, 2023
チャンスリーは非暴力で、警察のエスコートによる議事堂ツアーだけで4年の服役。
コメディアンのデイヴ・シャペルを舞台上でナイフで襲った男は罰金3,000ドルで刑務所なし。 pic.twitter.com/Hw23HfbzFK
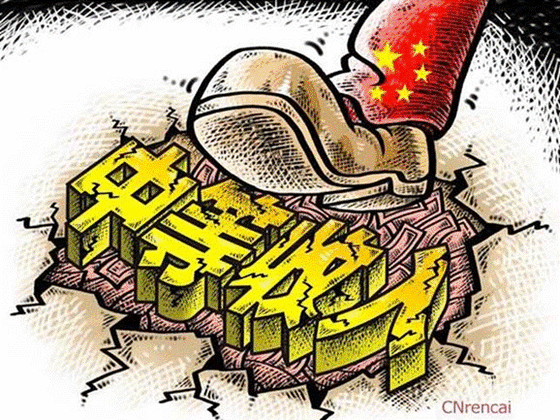



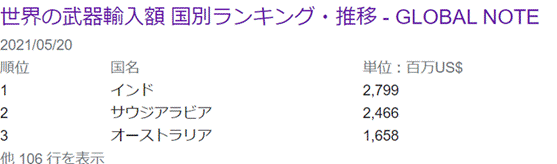



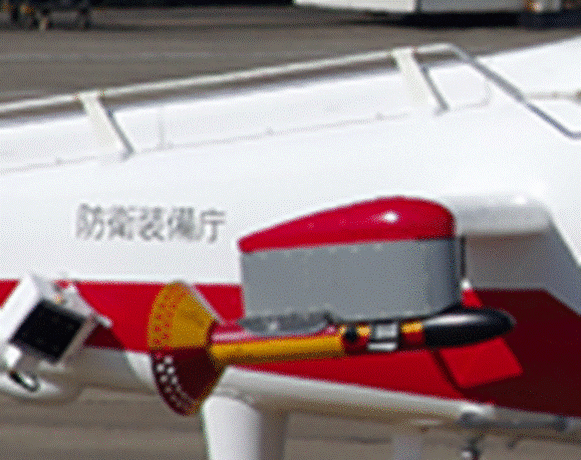
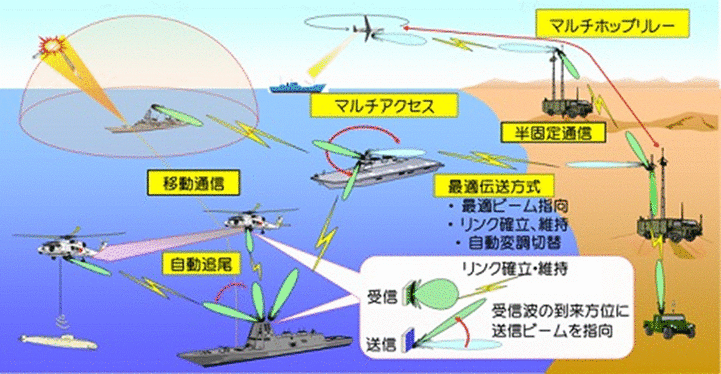
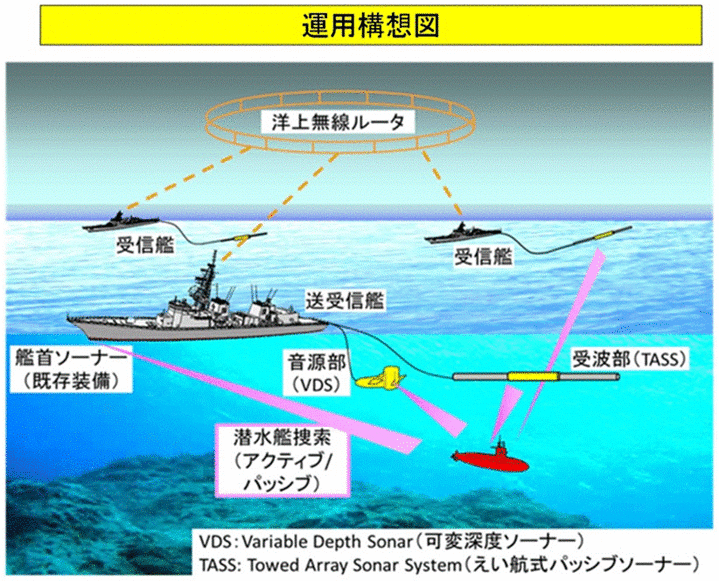
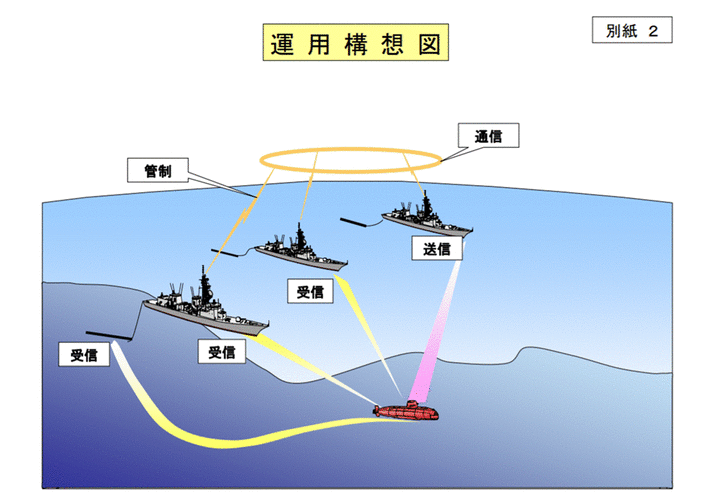
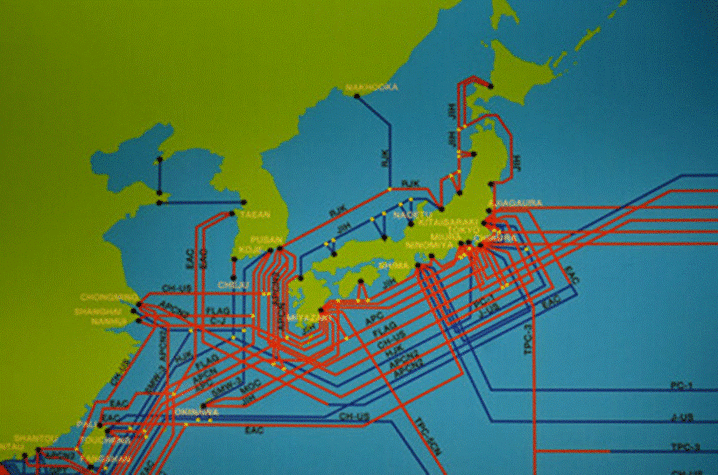
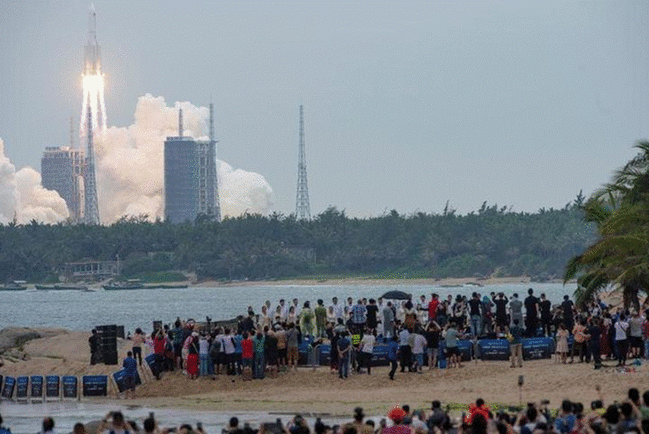
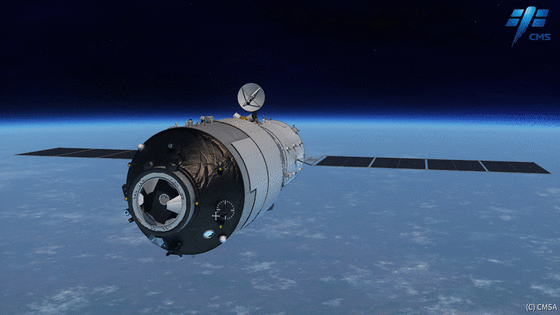
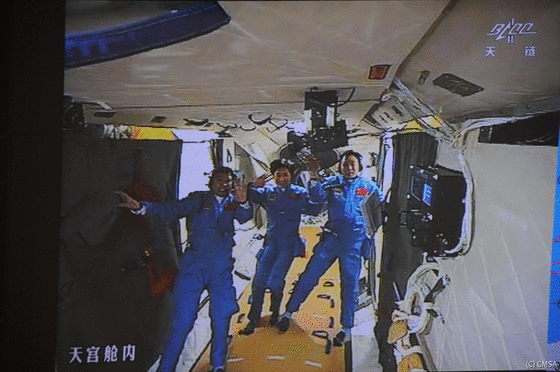
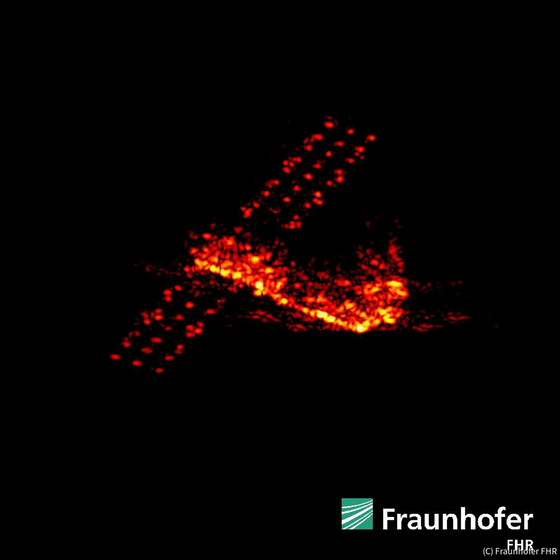
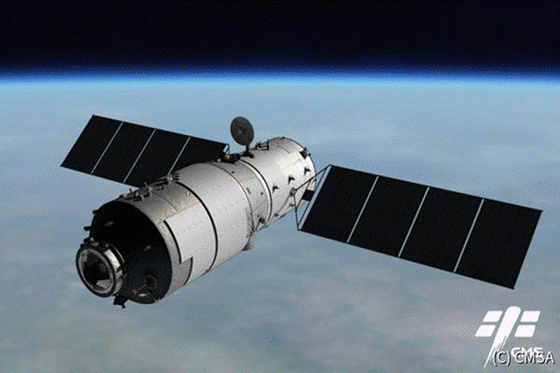

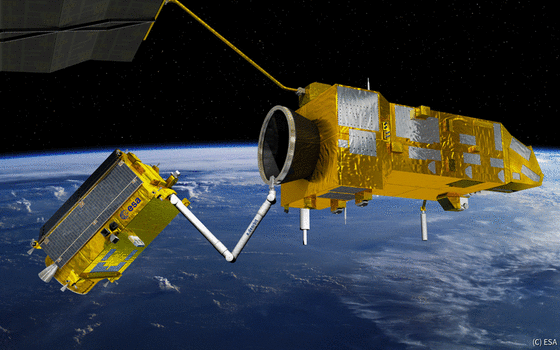
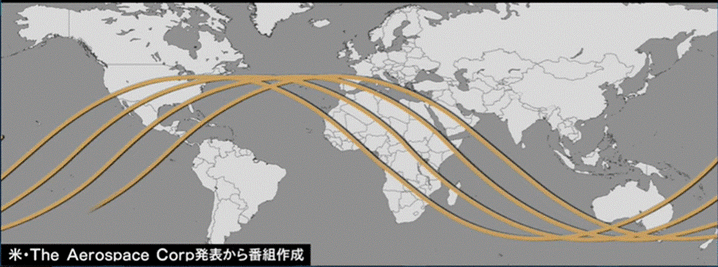
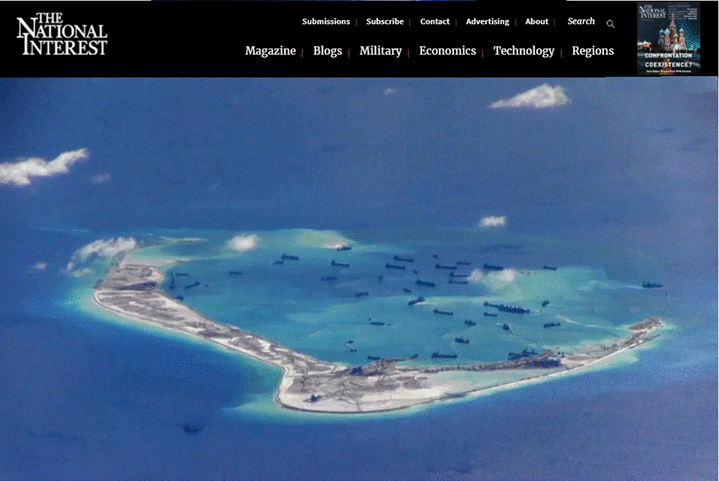

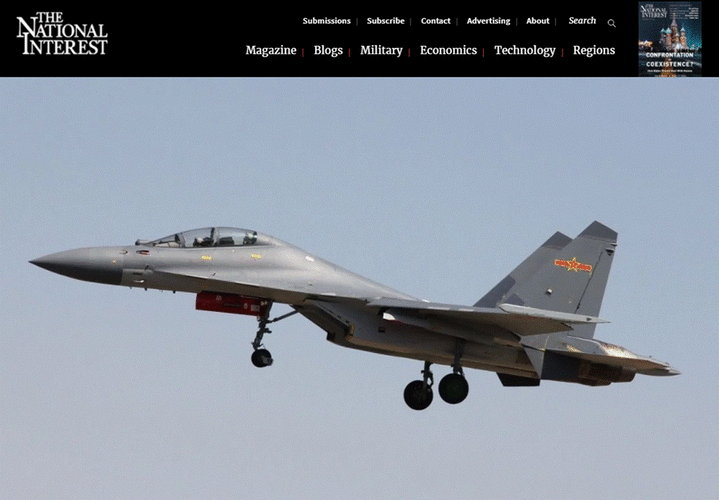
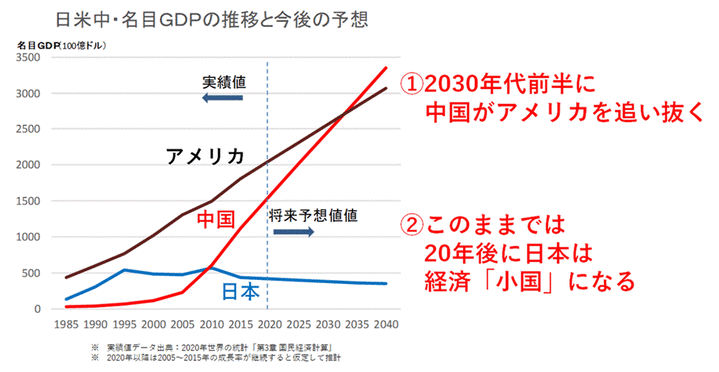

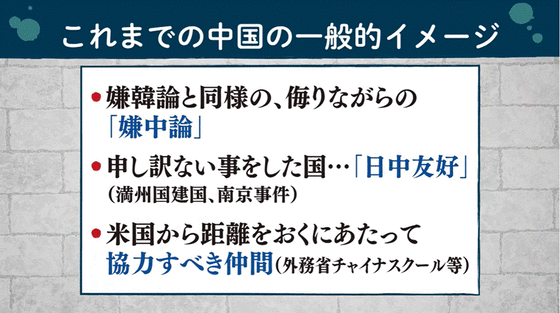
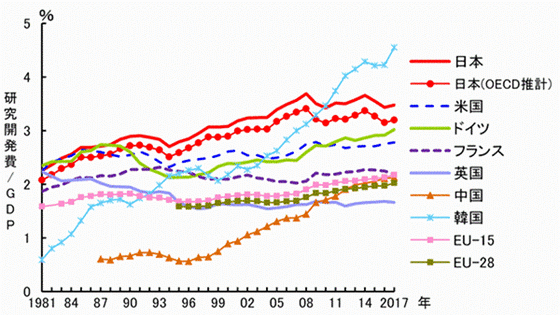

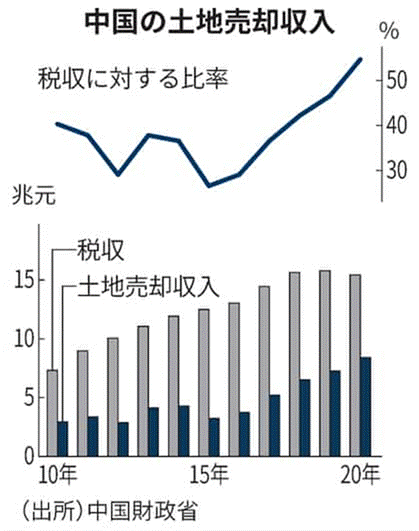
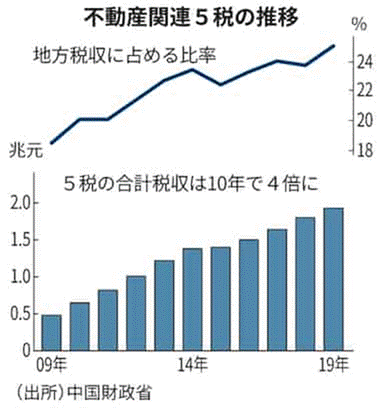
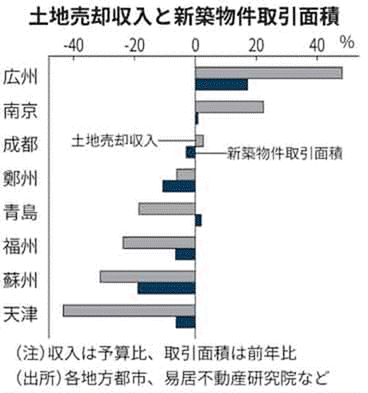
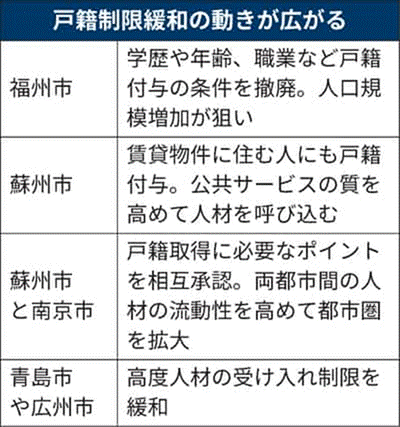
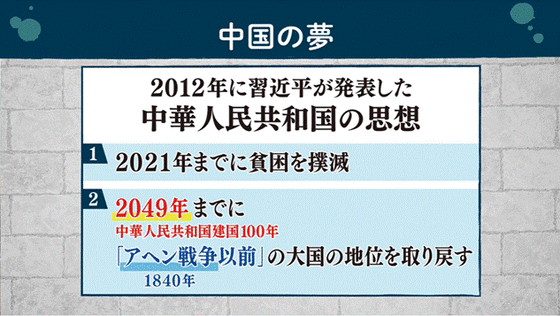
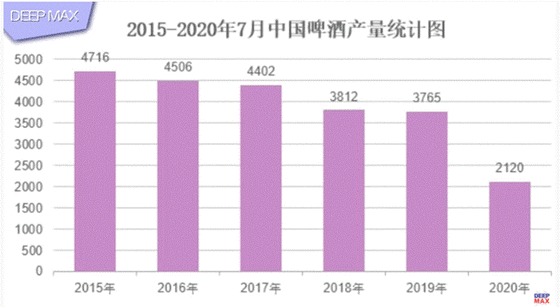
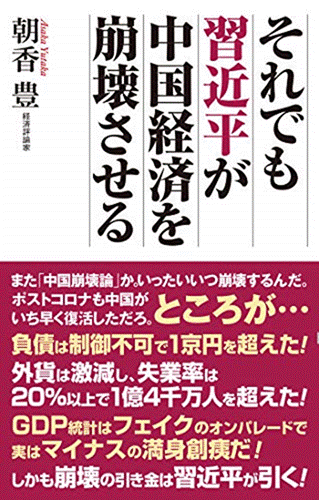
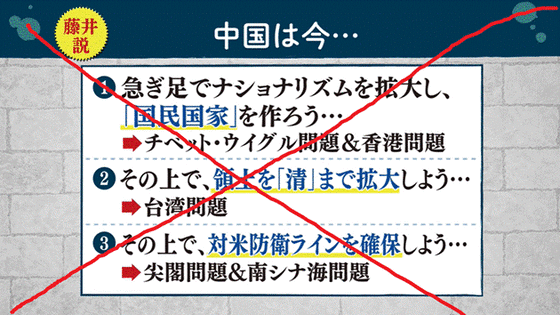
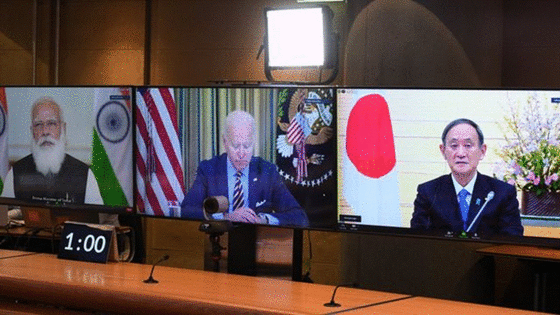
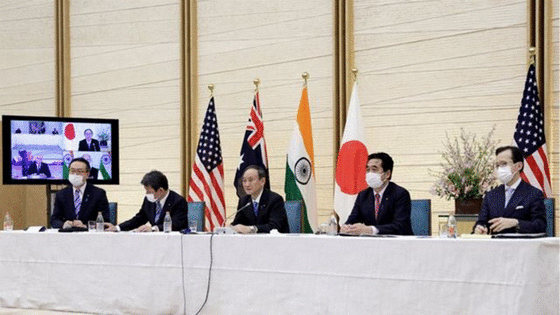

 現地 2020年3月9日
現地 2020年3月9日